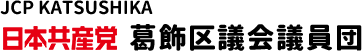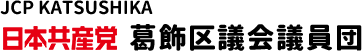日本共産党区議団を代表して一般質問を行います。
我が国の主食である米不足が本当に深刻です。政府は「備蓄米の放出は必要ない」「備蓄を供給すれば新米も含めて米価が下がり、農家が損をする」と言っていますが、あまりにも無責任です。米不足の根本原因は、毎年減産を農家に押し付けてきたからです。価格保障と所得補償の両面で、農家が安心して米づくりができる環境を整えるとともに、生産量を増やし、豊作などの際には国が買い上げて備蓄に回すなどの対策が必要です。
安定した米の供給のためにも区として政府に対して備蓄米の放出を求めるべきと思うがどうか。区内の子ども食堂や食糧支援に取り組む団体のために、区独自に米の支援をしてはどうか。
品川区では学校給食が無い夏休みの子どもたちの栄養不足を補うため、連携協定を結ぶ地方自治体から米を購入し、所得制限を設けずに小中学生一人2キロの米を配りました。本区も今後に備え連携協定を検討してはどうか。
米不足とともに物価高騰はますます深刻です。今月から1392品目の食品値上げ、さらに10月には3000品目もの値上げが予定されており、家計負担が増えることは避けられません。
今年6月に日銀が実施した第98回「生活意識に関するアンケート調査」によると、1年前と比べて現在の物価に対し9割以上の人が、物価が上がったと回答しており、5年後の物価も上がるだろうと回答した人が8割以上です。党区議団が実施した区民アンケートにおいても同様で7割以上の人が「この1年で生活が苦しくなった」と回答しており、その理由は物価の上昇がダントツで、次に税や社会保険料の負担に生活苦を感じていると回答しています。
実際、収入が少なく仕事がやめられない高齢者から「税や保険料の取り立てが厳しく生活できない」との相談を受けましたが、債権徴収強化により区民生活を脅かす、これでは本末転倒です。
補正予算案を暮らし応援の予算にすることも含めて、以下質問します。
- 江戸川区では昨年、非課税・均等割りのみ世帯の給付金対象外になった世帯に対して区独自の生活応援事業を行いました。高騰する食糧費に対応して本区でも現金給付等の実施。
- 個人・法人事業主に対して実施してきた給付金を増額して再度実施。
- 介護報酬の引き下げで訪問介護事業所は窮地にたたされている要介護者の生活を支えるためにも、特別に支援を行うこと。
- エアコン設置費助成は、修理も助成対象に含めて、期限を延長して受け付けてはどうか。また経済的不安でエアコンが使用できないのであれば、電気代助成。以上、答弁を求めます。
今後の自治体として在り方が問われる問題です。
第一に、公務労働のゆがみをただす改革が必要です。
本区の会計年度任用職員の8割が女性です。専門性の高い分野を担いながら、不安定雇用と低賃金に置かれ、ジェンダー平等を阻害する要因になっています。業務の民間委託も指定管理者制度も非正規労働者が多く、官製ワーキングプアを生んでいます。
シルバー人材センターのシニアも最低賃金から除外され、インボイス制度の適用も迫られています。
第二に、先の国会で成立した改定地方自治法による「指定地域共同活動団体」制度は、自治会やNPO、企業など地域の多様な団体に、区長が指定して財政支援を行い行政サービスの一部を担わせることができ、その業務は随意契約の期間の定めがないこと、「情報公開」の義務について疑問が残ります。首長が特定の団体を指定すれば、他の団体を排除や首長による特定団体との癒着も懸念されます。そこで質問します。
- 健康で人間らしい暮らしを送るための生計費を考えた場合、最低賃金は1500円以上必要だと言われています。区の会計年度任用職員の時給をそれにふさわしい水準で上げれば、8割の女性たちの生活が向上すると思うがどうか。
- 最低賃金が改定される10月に合わせて、シルバー人材センターに発注している業務の単価を上げてはどうか。
- 改定地方自治法に盛り込まれた「指定地域共同活動団体」制度のもとでも地方自治に守り、地方自治が補償されるものとして条例制定については拙速に進めるべきではないと思うがどうか。
子育てや若い世代への支援も重要です。
先程の区長挨拶から、来年度から修学旅行費などの無償化に踏み出すことは、わが党も兼ねてから要求してきたことであり評価をしますが、子育てにかかる負担をひとつひとつ軽減していくことが、若者の生き方の選択肢を広げることになります。そこで質問します。
- 第一子の保育料無償化について、区長は「かねてから考えていた」と述べました。そうであるならば、さきがけて実施してはどうか。
- 子どもが増えれば保険料負担が増える、このような制度は改善が必要です。国民健康保険料の子どもの均等割りの無償化も独自に実施すべきと思うがどうか。
- 若者の定住を促す家賃補助制度の創設や、空家を利用した若者向けの低廉な賃貸住宅など、本区に長く住んでもらうための新しい助成制度を創設してはどうか。
本区にとって学童保育クラブの待機児問題は、特別な課題として取り組まなければなりません。
なぜなら、こども家庭庁の調査によると、令和5年の待機児調査では、葛飾区は都内で最多の328人でした。今年4月の速報で待機児童は422人と100人も増え、待機児童の解消は全くできていないと指摘せざるを得ません。
しかもこの人数は「かつしかプラス」を利用する児童数が除かれたものです。「かつしかプラス」の案内には、「学童保育クラブのように、生活習慣の指導や学習指導、間食の提供は行わない」と明確に記載されており、学童保育クラブとは性質の違う事業です。だからこそ今年の予算審査では「かつしかプラス」の利用者は待機児童数に「含む」と答弁したのに、なぜ除いたのか、答弁を求めます。
私も、「かつしかプラス」の実施状況を視察してきましたが、一部では空き教室とも言えない、プールの更衣室を居場所として使っており、子どもが過ごす環境として疑問が残りました。支援員の方は限られた資源の中で子どもたちと過ごす努力をされていますが、おやつが出ないなど、制度の問題も残ります。
かつしかプラス入会者を加えると500人以上の児童が学童保育クラブの待機児となり、子どもの権利を侵害しています。学校内だけでなく、緊急増設すべきでありまた、公設公営の施設も含めるべきと思うがどうか。
次に水泳指導の民間委託について質問します。
まず新宿3丁目、お花茶屋1丁目に整備予定の屋内温水プールについてです。
私は、5月にオープンしたつくば市立みどりのプールを視察してきました。こ
の施設で水泳授業を行うとしていますが、本区と違うのは、学校の水泳授業優先の施設ではないということです。
第1に、整備の背景には、児童生徒数が増加している学校では校内プールだけ
では水泳授業ができない、学校プールの老朽化、スポーツと健康に関する市民の意識の高まりという観点から、学校プールの機能と合わせて、すべての人が利用できるように、社会体育施設として新設されました。
第2に、水泳授業は、午前中のみで当面9校を受け入れ、午後以降は一般開
放しています。
選定した学校は、バスで30分以内で移動できることを条件に、プール未設置
の学校、児童数が多くて校内プールでは賄えない学校、老朽化で使うのが困難な
学校が選定されています。その学校では、教員のプール管理・水質管理がなくな
り、監視員が1槽2名配置され安全面は向上したというメリットがあります。
水泳授業は、インストラクターはつかず、指導と評価の一体化の観点から教員
がおこなっています。今後、教員の指導力向上や安全管理体制の向上のために、県の実技指導者講習会への参加、体育学習アドバイザーの活用、指定管理者が設定する講習会の参加を促すとし、水泳指導で教員の果たす役割と責任に重きを置いていることがわかります。
学校優先の学校教育施設として整備し、水泳授業を民間委託している本区とは全く違います。
スポーツ施設としてのプール整備は区民要求も高く、本来なら歓迎されるべきものですが、先月、新宿、お花茶屋で開催された説明会では歓迎されるどころか、反対の声が続出しています。いずれも住宅地であること、プール建設先にありきになっていること、新宿は具体的な施設概要図までできて住民不在であること、お花茶屋は双葉中の第2校庭の要望を無視していること、整備費用が不明であることなどが出されています。
やはりプール建設先にありきで地域住民との合意がありません。
そこで質問します。
1、元々あった金町公園プールを屋内温水プールにする計画をそのまま実行すれば、新宿での建設を急ぐ必要はないと思うがどうか。
2、新宿でのプール建設は、プールのあり方も含めて地域住民との合意形成を最優先すべきと思うがどうか。
3、お花茶屋は、プール建設ではなく、当初の予定通り双葉中の第2校庭として整備すべきと思うがどうか。
4、双葉中学校の校庭は狭く、築年数も古く、改築校に選定し、改築と合わせて学校内に屋内温水プールを整備すべきと思うどうか。
2か所の屋内温水プールを整備し、20校を受け入れることが、いかに無謀な計画であるかは、この間の水泳指導の民間委託で浮き彫りになった数々の問題点からも明らかです。
現実に行われている学校プール活用の水泳指導の安全・安心対策不十分です。
学校外プールでは「着衣泳」が約半数で実施されず、夏季休業中の水泳指導は中止されています。
学校外プールでは、教員のプール管理がなくなりますが、学校プールでの負担は変わりません。文科省は、民間業者への委託で教員の負担軽減をするよう通達をだしています。
バス移動では、学校外プールに児童が置き去りにされた、3台配車予定が2台しか配車されなかった、契約外のバス会社が配車された、1校で4社のバス会社との契約など、バス確保に困難が生じているだけでなく、事故が起きても区教委に報告すらされていません。移動が予定通りいかず休憩、給食に支障をきたしています。
学校外プールを活用すれば、その施設の一般利用者が排除される事態が生じ、水元温水プールやセントラルフィットネス青砥店の利用者から、繰り返し請願が出される事態が続いています。
広報では、児童が温水プールの水泳指導を「楽しい」との回答を強調していますが、9%約600人は「楽しくない」と回答に分析がありません。
子どものアンケートでは「インストラクターが怖い」という回答と合わせて、教員のアンケートにも「なぜ大きな声で叱られたのかわからない、怖い、と訴えた児童がいた」「乱暴な言葉遣い、威圧感を感じる指導」があったと、子どもへのハラスメントの実態が告発されていまが、区教委は「ハラスメントの声は上がっていない」と開き直っています。
何よりも水泳指導は命を守る教育であり、民間委託でいいのかが根本的な問題です。
区教委の「手引き」には、「現場でのインストラクターへの直接的な指示命令は契約上できない」と明記しているのは偽装請負になるからです。そのためインストラクターのハラスメントに気が付いても教員は指導できません。その点からも安全に関わる教育を学校以外の人材に任せることは、命への責任の放棄になります。
スイミングスクールのインストラクターの指導は第一に泳力をつけるためのトレーニングです。一方、学校が教育として行う水泳の指導は、泳力だけでなく、呼吸の確保、浮く姿勢などを核としながら、川や海で過ごすことも視野に入れた命を守る教育です。奥戸温水プールの指定管理者は住民との懇談で、「先生がきちんとプールサイドにいてみんなを見守り、最初と最後に先生があいさつをしっかりおこなう」と語っているように、水泳指導の中心をインストラクタ―任せでは、「命を守る教育」とは言えません。
水泳指導の民間委託は、様々な問題があり、学校間格差をつくるものです。そこで質問します。
1、小中50校の学校プール活用校でも熱中症や天候を配慮して、遮光ネットや屋根、プールサイドへのテント設置などの対策を講じること。
2、水泳指導を教員が行う上でも体制の強化を図ること。
3、着衣泳の実施は、海や川での事故が増える夏以前に全校実施すること。
4、夏季休業中の水泳指導は学校判断ではなく、社会教育としてできるよう環境整備を行うこと。
5、学校プールの管理は、業者委託で教員の負担軽減を図ること。
6、学校外プール活用で、一般利用者から声が上がっている場合は、当該プールの活用をただちに中止すること。
7、子どもへのハラスメントは人権侵害であり犯罪行為です。契約書に対策を明記すること。
8、教員の指導力向上のために、研修やアドバイザーの活用などを検討すること。
9、水泳指導は命を守る教育です。3年におよぶ民間委託の全面的な検証をすること。以上、答弁を求めます。
次に、森永乳業東京工場跡地の巨大物流倉庫が本区の環境に与える影響について質問します。
森永乳業東京工場跡地に、延べ床面積約16万6998㎡、マンション12階建てに匹敵する、高さ36m5階建ての巨大物流センターが建設されようとしています。巨大物流センターは、24時間稼働で、一日に約5000台の大型トラックや貨物車両などが頻繁に往来します。
ここは、森永工場内の多数の樹木、閑静な住宅地、小学校、学童保育クラブ、保育園、図書館、福祉施設などがあり、住民からは、環境や交通の安全面、騒音や振動、日影など、重大な影響に不安な声が上がっています。
巨大物流センターができることで、どう変化を予測をしているか。葛飾区にとってどういう影響を及ぼすのかを予測し、その対応が求められているに、この間の総務、建設委員会でもその影響は明らかになりませんでした。
昭島市でも、巨大物流センターができることで、CO2排出量は昭島市全体の約4倍と調査報告が出ています。本区と昭島市とでは、面積も人口も物流センターの規模も異なりますが、環境アセスを実施したことにより、環境に与える変化を予測しました。
しかし、本区では「計画に影響があるような形でCO2の排出量が増えていくというのは考えづらい」と答弁し、まったく無関心、無神経な態度といわざるを得ません。
交通量の変化や新たな渋滞の予測など、この森永工場跡地周辺だけではなく、新設される補助284号線沿線やこの道路に接続する蔵前通り、環七などにも大きな影響が及ぶことも予測されます。
こうした巨大物流センターを建設には、環境影響調査・アセスメントを行うことによって、その影響を見定め、効果的な対策を探求することが重要です。この環境影響評価は、よりよい環境保全の観点から望ましい事業計画をつくる制度です。この案件は、重大な影響を及ぼすことは明白であり、環境影響評価を実施させるべきと思うがどうか。
第三次環境基本計画では、「ゼロエミッションかつしか」の達成を目指して喫緊気候変動を無克服するためのむ指標や取り組みの目標を区民と事業者、区自身の取り組みをあげて進める方針を掲げましたが、この物流センターの建設と完成後、大量の大型トレーラーとトラックの往来が、目標達成の障害となるのではないかと危惧をするものです。
その第一は、業務部門からの温室効果ガス排出量も含めて、2030年までに半減するとしていますが、むしろ増大する危機とならないかと思いますが、どのように考えているのか、答弁を求めます。
第二に、森永乳業東京工場跡地は、64年の歴史に育てられた大量の樹木は、ほとんど伐採され、その影響、CO2吸収量の減少はどうなったのか答弁を求めます。
環境対策としてのCO2吸収量の拡大のための具体策の提案です。千葉大学 藤井英二郎名誉教授は、「街路樹の樹冠が道路を覆えば、直射日光があたる道路より路面温度が20°も下がる」いかに、「高木の枝葉で直射日光を遮ることが重要」と言っています。
高木の枝葉が覆う面積割合である、樹冠被覆率を明確な目標として増大することが“地球沸騰化”における重大な対策であり、世界では、樹冠被覆率を明確に位置付ける流れとなっています。本区としても、急いで樹冠拡大に取り組むべきではないか。
樹冠被覆率の重要性をどう認識をしているのか。面的把握(緑被率)に加え、土地面積に対して枝葉が茂る部分が占める割合である、樹冠被覆率の明確な目標を位置付けるべきと思うがどうか。
第三に、街路樹の位置づけを抜本的に改めてはどうでしようか。
桜などは切らない方がいいという考えが定着しており、街路樹の樹冠は大きくし、きちんと手入れをすれば、寿命は80年と言われています。
なかでも、落葉広葉樹のユリノキは、大気中のCO2を効率的に吸収して蓄積する能力が高く、ユリノキが出現したところ、大気中のCO2の濃度が急激に減少することが明らかになっています。気候変動に対応できる樹木を増やすためにも、区内の街路樹をユリノキなどに変える策があるのではないのか。
落葉についての対応として、中野区では1978年「緑の保護と育成に関する条例」が制定されました。条例の中に「維持管理等の義務」として「区民はあまねくみどりの効用を享受するものとして、所有者の管理が及ばない落葉については、これを受忍しなければならない」とされています。緑を守るためには非常に大事な視点ではないでしょうか。
したがって、今後の街路樹の剪定計画や植樹の維持、新たな植樹を環境対策として、住民合意で取り組み、数値目標も持つべきと思うがどうか。
昨年策定されて都市計画マスタープランでもすでに森永乳業東京工場が閉鎖された後のことであり、その跡地活用については、「安全で便利なまちづくり」と記載されました。しかし、今日、地域で説明されているこの工場跡地利用は、マスタープランに掲げられた方針とも合致したものとは言えません。したがって、この土地の活用については、一旦、立ち止まるべきではないか、答弁を求めます。
次に、平和について質問します。
核兵器禁止条約は、核兵器を全面的に違法とする世界初の国際条約です。2010年10月に条約発効に必要な50ヶ国が批准し、2021年1月に新たな国際法として発効し、その後も新たな加盟国も増加し、署名国は93、批准国し70に達しています。
しかし、唯一の戦争被爆国である日本は、この条約に参加していません。
平和首長会議に参加している区長が、「非核平和都市宣言区」の区長として、今こそ政府が条約批准のために主導的役割を果たすべきではないでしょうか。
さて、2025年度(令和7年)は、被爆80年という節目の年を迎えるにあたり、被爆の実相の継承、恒久平和の実現、非核平和に向けて更なる、平和啓発活動と非核平和事業拡大すべきであり、以下の事業に取り組むことを提案します。
1.区役所区民ホールや地区センターなどで、原爆写真ポスター展や原爆関連記録映像の上映をしていますが、継承する貴重な取り組みとして、各学校や公共施設などで実施すること。
2.原爆が投下された8月6日・9日、8月15日終戦記念日と、3月10日東京大空襲も含め世界の恒久平和を祈念し戦争の記憶を風化させないよう、区内全域に防災行政無線を活用し黙祷を呼び掛けてみてはどうか。
3、青戸平和公園に、非核平和のシンボルとして「平和の鐘」を設置すること。
4.次世代を担う中学生に、平和の大切さを伝えるために、中学生代表派遣を再開すること。広島、長崎への修学旅行も積極的に推奨すること。
5.旧教育資料館を保存・修繕し公開すること。郷土と天文の博物館で、終戦80年であり特別展示会を検討すること。
6、核不拡散条約(NPT)再検討会議に区民団体などを派遣すること。
7.次世代に繋ぐ平和への思いを、来年1年かけて記録に残し、記録集や祈念誌などをつくること。
最後に、立石駅北口再開発・庁舎問題について質問します。
7月19日、東京地裁でこの再開発に関する、集団住民訴訟第一回公判が行われました。葛飾区民だけではなく再開発関係者や、またマスコミにも注目され、約100名収容することのできる東京地裁の103号法廷には、傍聴者が多数つめかけ、傍聴券の抽選が行なわれ、103号法廷は、満杯となりました。
東京地裁で第二回公判の予定は10月30日の予定となっています。
先の定例会では区議会第二回定例会で「権利変換」後に杜撰な計画だったために工期が1年5ケ月延長するという事態となり、事業費等が高騰するのでは、という疑問が上がり、事業費、保留床価格を8月に変更を報告すると答弁がありました。これは、区政における大問題だからこそ、この間、全協の開催や区役所の位置条例の議決など議会が慎重な対応をしてきました。今定例会の冒頭の区長発言でもしかるべき説明があって当然だと思いますが、一切の説明がないことは不誠実です。
とりわけ、前回区長・区議会議員選挙直後の「広報かつしか」の2022年1月15日、5月25日、10月15日でくりかえし242億円で庁舎保留床を購入し、庁舎を移転することができると大宣伝してきました。ところがその大前提が崩れたわけです。このことについて、区長の認識について答弁を求めます。
しかし、その後、情報提供が、立石駅北口再開発組合が示した計画変更案として説明を受けました。その工事の完了を見通した工事費の価格としなければ、合理的な見直してして、庁舎保留床どれだけの税金投入されるのか、地権者も将来の見通しが立たないということになってしまいます。
現に江戸川区では、当初300億円と言われていた総工費の工期を延長し、諸物価の高騰を鑑みて、590億円の建築費が必要と公表しました。
工期の完了を見通した資金計画の変更を示さなければ、誠実な計画変更と言えないのではないか、答弁を求めます。
また、そうした合理的な説明がなければ、区役所の位置条例の一部を改正する条例について、区民から疑問の声が寄せられるのは当然です。そうなれば、2022年12月の区役所の位置条例の議決は、不変ではなく、再開発組合による新たな合意への検討も葛飾区側から求めることも検討すべき段階にあるのではないか。
現「位置条例」の位置を決定する期日の「施行規則」とされているが、その施行規則は、議会のの声を広く聞き、判断材料とすべきと思うが、答弁を求めます。
東京地裁での集団住民訴訟は単に、「権利変換計画への異議」にとどまるものではありません。
事業費は物価高騰だけではなく、計画性が欠ける「権利変換計画」の承認を急いだために、不合理な事業費となり、かつ、一年5ケ月延長したために事業計画よりもさらに高額となり、現時点の事業費見直し案からも現実のものとなりました。
今後、区役所庁舎とする保留床の価格も高額となることは自明のことであり、この事業の計画を見直すことは、今後の区有財産の散逸を防ぐためのものであり、住民として当然の正当性をもつ訴えであると思うが、区長の見解を求めます。