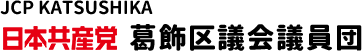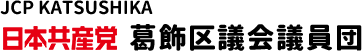日本共産党区議団を代表して一般質問をします。
今、自民党の裏金作りに対する国民の怒りが沸騰しています。それは、この間の衆院3補選、目黒都議補選、港区長選でも現れました。目黒都議補選では小池知事は自民党を応援しました。青木区長は、その小池知事に出馬要請していますが、いずれも都民、区民の厳しい批判は免れないという事をまず申し上げておきます。
さて、総務省が発表した4月の消費者物価指数は2.2%上昇し、32か月連続上昇しています。特にキャベツや調理パン、ガソリンなど、身近な品目ほど大きく値上がりしています。民間シンクタンクのみずほリサーチ&テクノロジーズは物価高騰で24年度の家計負担は23年度に比べて10万円超も増えると試算し、帝国データーバンクのまとめでは、23年度の物価高倒産は過去最多を更新し837件発生したとしています。その上、7月から電気、ガス代の値上げは、区民生活や中小企業の経営にさらなる悪影響を与えることは明らかです。
今、身近な区政がやるべきことは、区民のくらしと営業を守るために物価高騰への抜本的な対策を講じることです。
そこで質問します。
1,この間、実施してきた個人事業主、法人事業主への現金給付事業について給付額をあげて第3弾を実施すること。
2、税や保険料の値下げが必要な時に、区は、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料を全部値上げしました。保険料の引き下げのために一般財源の投入など思い切った対策をとること。
3、低所得世帯へのエアコン設置助成は、これまで求めてきたものですが、いったん自己負担させる償還払いでは日常生活に支障をきたします。区と事業者との間で支払いが済む制度にすべきです。また電気代の支払いを気にしてエアコン使用を躊躇しないよう電気代の支援をすること。
区が実施したアンケートによると、子育てに伴う経済的負担の軽減を求める声は49.5%、進学のための経済的支援を求める声は56.4%と、前回より5%~9%アップしました。
この声に応えるためにも、1、学童保育クラブ使用料、第1子の保育料、中学校の修学旅行費の無償化に踏み出すこと。
2、中野区では、非課税世帯に対して8万円の高校入学支援金事業を実施するとしています。足立区では奨学金返済支援として借入額の半額まで助成する制度があります。本区でも奨学資金貸付に対する返済支援制度を構築し、中野区のように返済不要の支援金も実施して、要返済から返済不要へと奨学金制度を移行すること。
3、国の児童手当や児童扶養手当が4か月に1回から2か月に1回支給に変更になります。これに合わせて区の児童育成手当も支給月を変更すること。以上、答弁を求めます。
次に、子どもの権利条例にもとづく子どもの施策について質問します。
まず共同親権についてです。
国会では共同親権制度が成立しましたが、子どもの意見表明権や子どもの意思の尊重が含まれていない、DV加害者の親権が完全除外されていない、一方が拒否すれば子どもの不利益につながるなど、子どもの権利や安全が損なわれるといったおそれがあります。
本区では、同法の施行後、子どもの権利を守るために、どのように相談や調整にあたるのか、答弁を求めます。
第2に子どもの「居場所」についてです。
青戸子ども総合センターと金町子どもセンターには、「子育て広場」があり、子どもの育ちを支える拠点となっています。
わが党区議団に、この施設の利用者から「平日は仕事で、土日はワンオペ育児のために、せめて日曜日の午前中だけでも、子どもセンターを利用できるようにして欲しい」と相談がありました。利用者の方にご意見を伺ったところ「もし日曜日も開いているなら絶対に来ます」と強い要望がありました。
子どもの権利条例12条では、「育ち学ぶ施設が子どもの健やかな成長に重要な役割を持っていることを認識し、区、保護者及び区民等と協働、連携し、子どもの健やかな支援をするよう努めます」とあります。子育ては週7日間365日、休みなしです。
そこで質問します。
1、子ども総合センターと金町子どもセンターを子ども未来プラザと同様に休日も開館すること。
2、児童館も、20か所の地域型児童館は毎週日曜日が休みです。地域型児童館の日曜日開館を拡げること。
3、新小岩1丁目~4丁目に児童館の復活を望む地域要望に応えること。
4、子どもたちがのびのびと遊ぶことのできる場所を保障するために、「子ども未来プラザ」は児童厚生施設として条例で位置付け、施設運営を支える職員の処遇改善も図ること。以上、答弁を求めます。
第3に、保育所についてです。
新基準の待機児が今年度も「ゼロ」でしたが、旧基準では、325名であり、真の待機児解消には至っていません。特に一歳児保育の拡充は待ったなしであり、定数の拡充が必要と思うがどうか。
大規模マンションが建設された新宿6丁目は、0~5歳児の人口が、2019年5月は621人、2024年5月は752人と増加が顕著です。
港区では延べ面積が3000平方メートル以上の開発建築物に義務的に設置すべき施設を例示し、保育所等の子育て支援施設の設置を促進していますが、本区でも大規模集合住宅建設の計画地域もあり、港区を参考にして検討してはどうか。
第4に、学童保育クラブについてです。
学童保育クラブの待機児は毎年増え続け、大規模化に伴う環境悪化など、思い切った増設でしか解決できないのに、その立場に立っていないことが問題です。まず4月1日現在の待機児は何名になっているか伺います。
子どもの人口増加は、その数年後の学童保育クラブ利用対象にもつながります。待機児解消は、民間任せではなく、区が責任をもって増設すべきと思うがどうか。
都営住宅の1階にあった飯塚学童保育クラブは、飯塚小学校内に移転しましたが、定員いっぱいの状況が続いています。そのため、申請をあきらめてしまう保護者もいます。南新宿学童保育クラブを廃止して、学校内学童保育クラブに統合した時も同じことが起き、未だに解決できていません。区立学童保育クラブの全廃方針の撤回が必要と思うがどうか。
国は学童保育の監督官庁を、文部科学省からこども家庭庁に移しました。本区の子どもの権利条例を生かしていくためにも民間学童保育クラブの所管を教育委員会から子育て支援部に一本化すべきと思うがどうか。
次に、防災対策について質問します。
わが党区議団は、先月20日、21日に能登半島地震の被災地の視察とボランティア活動を行ってきました。
5ヶ月以上が過ぎても、住宅の倒壊、道路の陥没、ガレキはそのままなど、地震直後と変わらない光景が至る所に存在し、全焼した輪島朝市は言葉にもならない状況でした。被災者を取り巻く環境は日を追うごとに厳しさを増しています。
ボランティア活動は、2か所の仮設住宅を一軒一軒訪問し、要望を聞き取る活動でした。「公費解体の申請をしてもいつやってくれるのかわからない」「高齢で借金をしてまで家を建てることができない」「仮設住宅は2年で出ることになる、公営住宅をつくってほしい」「仮設住宅が狭く荷物が入らない」「隣の音が聞こえる」などが共通した声でした。
災害関連死は30人と発表されていますが、不便なトイレと体を伸ばして眠ることもままならない生活環境や感染症によるものが目立ちます。被災者の人権やプライバシーを守るスフィア基準にもとづかない我が国の劣悪な避難所環境や仮設住宅の狭さが命を左右していることがわかります。
まず避難所等についてです。
第1回定例会でのわが党の質問に、「良好な避難所環境の実現に向け検討している」との答弁がありました。
良好な避難所はスフィア基準で明確です。あとは具体化するだけです。避難所・避難生活学会は、清潔で洋式のトイレのT、温かい食事を提供できるキッチンのK、段ボール等のベッドのBを発災時から48時間以内に避難所に届ける「TKB48」を提唱しています。
第1にトイレです。
断水が続きトイレが使えない中、全国からトイレトレーラーの支援がありました。平常時はイベントなどでも活用でき無駄がありません。本区でも配置してはどうか。
第2にキッチン、食料の備蓄です。
災害時に温かい食事を提供することは心のケアにもなります。長野県内の自治体では、キッチンカ―を保有し、災害時以外には、まちづくりを担う団体に貸し出したり、地域特産品のPRのために活用しています。本区でもキッチンカ―を導入すべきではないか。
足立区では、食料や水の備蓄量を、2027年までに現状の1.5日分から3日分に増やす計画です。本区でも3日分以上の備蓄を検討すべきと思うがどうか。
第3にベッドやテントです。
日常生活でもベッドが欠かせない区民はたくさんいます。また避難所であっても人権やプライバシーは守らなければなりません。本区では授乳などのためにテンは確保しているとしていますが、各避難所に段ボールベットや世帯ごとのプライバシー保護のためのテントを確保する年次計画を持つべきと思うがどうか。
第4に、防災ラジオです。
聞き取りの中で、「電気が通らずテレビがつかない、唯一の情報源はラジオだった。一日中つけっぱなしだった」との声があり、ラジオが支えになっていることがわかります。区民に早く正確な情報を伝達するためにも防災ラジオを配布すべきと思うがどうか。
第5に、災害時の入浴です。
被災地では、一部の公衆浴場や公共施設に併設された風呂が無料で利用できる支援制度が始まっています。仮設住宅では「一人で入るより、みんなの背中を見てお風呂に入った方が、何ぼも元気になる。知り合いに会えて心の支えになっている」との声がありました。
本区のシニア活動支援センター、水元学び交流館の入浴施設は、現在利用できません。必要な修繕を急いで行い利用できるようにすべきです。新小岩地域には風呂がなく公衆衛生に格差があります。公共の入浴施設をつくるべきと思うがどうか。
次に液状化対策についてです。
液状化によって建物倒壊、道路の損壊など甚大な被害が発生しました。
本区の被害想定でもほぼ全域で液状化が発生する可能性が高いとしています。そのため地盤調査に係る費用の助成や相談窓口の設置を行っていますが、対策は進んでいません。
液状化の極めて高い地域では、区が率先して地盤調査を行い、対策が必要な住民には率直に訴えてはどうか。また区内のすべての車道と歩道の液状化対策はどうなっているのか。
次に、生活再建についてです。
被災者再建支援法に基づく支援金は最大300万円です。しかも全壊と大規模半壊に限られ、半壊、一部損壊は対象外です。石川県内では、公費による解体が申請の1%未満にとどまっています。被災者再建支援法に基づく支援金の支給限度額や対象の拡大、公費解体がスムーズにできる環境整備を国に求めるべきと思うがどうか。
災害対策に関係する問題として地方自治法の一部改正があります。「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば、国に地方自治体への指示権を与え、自治体を国に従属させる仕組みをつくるものです。しかし、「重大な影響を及ぼす事態」とは何かの定義はありません。杉並区長は「災害や感染症のまん延時に重要なことは、自治体同士が連携し、住民の命と財産を守るために主体的に取り組むこと」「自治体の能力を過小評価しているのではないか」と指摘しています。国と地方の関係は対等・協力であるべきで、拙速な改定はすべきでないと思うが、区長の認識を伺います。
次に、都市農業について伺います。
我が国の農業は、自民党政治による歯止めのない輸入自由化によって、食糧自給率は38%に落ち込み、25年間で農業従事者は半減、53万ヘクタールの農地を失いました。本区でも2013年には農業者世帯数は190世帯から22年度には163世帯へ、農地面積は41.56haから34.10haへと減少しました。
私は、この間、区内の農家の方々を訪ねてきましたが、「人間が生きていくうえで必要な食料やエネルギーは自国でまかなうべきだ。そのために所得・価格保障などは当然だ」というご意見をいただきました。今やるべきことは、政府の責任で所得保障、価格保障を行い、再生産を支える仕組みを作り、食料自給率の向上を国の最優先課題にすることです。
ところが先月29日成立した改定食料・農業・農村基本法は、際限のない輸入自由化への反省もなく、低迷している食料自給率を向上させるものになっていません。
ご存じのように農業は、食料だけでなく環境、景観、交流、防災など、また2024年問題との関係でも地産地消という都市農業の果たす役割はますます重要になっています。
夏の猛暑の下で区内農家の方々も大変苦労されています。「先祖代々から受け継いだ農地を失うわけにはいかない」「猛暑の時期は休むしかない」という声は共通していました。「枝豆なら収穫して持ち帰って作業できるので、夏場は枝豆、夏以外は小松菜に切り替える」「学校給食に小松菜を納めている。長さによって味が違うので、栄養士さんからのリクエストにも応えている」、30代の後継者の方は「ブルーベリーなど果樹で頑張って葛飾を盛り上げていきたい」と頼もしい声など、安心でおいしい食料を、との思いが詰まっている声ばかりでした。
こうした声に応えるべく、本区もJA東京スマイルとの協定、「葛飾元気野菜」のアピールや直売所、即売会、農業体験農園、ブルーベリー観光農園、農業応援サポーターなどの取り組みがあります。
この取り組みをさらに強め、本区の都市農業を守り発展させていく立場から質問します。
1、本区における都市農業の位置付け、農地保全についての考えを伺います。
2、現在取り組んでいる様々な事業についてより一層周知をはかるとともに、直売所を増やしてはどうか。
3、猛暑の中でも、少しでも農作業がしやすいように、建設現場で見られるようなスポットクーラー購入支援など実施してはどうか。
4、後継者難から残念ながら農地を手放さなくてはならない事態になっても、都市農地貸借法では、農地を貸した場合、納税猶予制度が継続されるため、区民農園として活用できると思うがどうか。
5、昨年の区民と区長の意見交換会では有機野菜を学校給食に使ってほしいとの要望がだされていましたが、有機野菜についての区長の認識を伺います。 6、東京都では、化学合成農薬と化学肥料を削減してつくる野菜を「東京都エコ農産物認証制度」として実施し、本区でも取り組んでいる農家の方がいます。葛飾元気野菜とともにエコ農作物をアピールし、農家の方々の意見を聞き区として更なる支援をおこなってはどうか。以上、答弁を求めます。
次に、立石駅周辺の再開発と庁舎移転計画について伺います。
さる2月29日に立石駅北口再開発の権利変換計画に係る240名余の住民監査請求が提出されました。その内容は、区が取得する東棟3階部分の権利床があまりにも高く、区民に損害を与えているというものです。
再開発の床価格は、上階が安価になります。西棟では、1階の商業床より2階商業床や3階の区が取得するバンケットホールが安くなっています。
一方、東棟では、区が取得する3階部分の権利床は、1㎡あたり988,215円、同東棟の2階は、1㎡452,234円でした。さらに、1階の警視庁の権利変換価格よりも高いという矛盾したものです。区の権利床部分はスケルトンではなく、建設費込との答弁ですが、そうだとしたら、その部分に対する予算執行の手続きがないことは不合理です。
住民監査請求では、2階の権利変換計画との差額分の約7億円の弁済を求める請求でしたが、監査委員は、3月21日に監査しないと棄却しました。
棄却理由の一つに、今後、資金計画の見直しが予定されていることから「損害金額が明らかでない」としていますが、すでに工期の1年5カ月の延長による補償費の増加、資材や人件費の高騰によって資金計画が膨らむことを区も認識しており、損害ははるかに膨らんでいくことは確実です。
住民監査請求とは、そうした損害を未然に防止するための地方自治制度であるのに、その責任を放棄しているといわなければなりません。
住民監査請求をすすめてきた市民団体は、名称を「新庁舎問題/住民訴訟を進める会」とし、東京地裁に238名を原告とする集団住民訴訟を提訴しました。同日、記者クラブで記者会見が行われ、その報道が注目されています。今後の審理は、東京地裁で最も大きな第103号法廷で行われることになりました。
先の定例会では、大阪万博でも、江戸川区役所でも建設費が2倍近くに跳ね上がっている例を示し、再開発組合の試算の公表を求めたところ、8月頃と答弁しましたが、これは極めて不誠実です。
東京北区では、公共施設の「北とぴあ」の大規模改修も100億円を予定していましたが、工事費が2倍近くの190億円になることが明らかになり、その事業費を抑えるために、改修工事の大幅な見直しが検討されています。
本区の場合、広報を使い区庁舎が240億円程度で駅前に移転できると繰り返し宣伝しただけに、この費用問題は、裁判闘争でも避けて通れません。それだけに、区民にいちはやく、今後の見通しがどうなるのかを知らせる責任があります。すでに、再開発組合には、工事の見積もりが提示されているのですから、それをただちに公表すべきと思うがどうか。
権利変換した地権者を放置することはできません。なぜなら立石駅北口再開発は、もはや破たんした計画でありながら、区庁舎を移転することで葛飾区が多額の税金投入によって地権者を誘導し、借家人を追い出し、強引に計画を進めてきたことに道義的責任があるからです。このまま今の計画に手を付けることなく、漫然と税金投入することとなれば、全区民に被害を及ぼすことになります。
それを避けるためには、都市計画決定と庁舎のあり方を含めた計画を抜本的に見直し、その新たな計画を全地権者で合意を取り付ける責任があると思うがどうか。
人工的に街壊しを進めたことを反省し、賑わいを取り戻すために必要な事業展開がいまこそ必要です。
わが党区議団は、4月23日、立石駅北口再開発によって南口にどんな影響がでているか、また南口の再開発について南口商店街の聞き取り調査を行いました。
「立石では人の流れが変わり、完全に全体数の減少が著しい、もちろん客も激減した」「数年前に北口から南口で商売を始めた。絶対反対」「生活再建のための補償が受けられるまで商売が続けられるかどうかが心配」などと悲痛な叫びがありました。
立石のまちの賑わいはすでに深刻ですが、駅南口東地区の権利変換計画、その後、北口と同様に解体工事のためのバリケード囲いをすることになれば、今以上、深刻な状態になることは、だれの目から見ても明らかです。
それなのに区長は、先ほどのあいさつで漫然と南口の再開発について述べていますが、駅南口再開発計画は、まず、凍結すべきと思うがどうか。
いま直ちに行うべきは、立石駅周辺の街の賑わいを再興するために区が積極的なイニシアチブを発揮するための事業に取り組むことです。
たとえば北口の計画道路エリアや奥戸街道の空き店舗を活用するなどして、街の賑わいを取り戻す努力をすべきと思うがどうか。答弁を求めます。
次に高砂団地建替え跡地について質問します。
高砂団地建替え事業は、11年前から新しい住宅へと移転が始まり、あと1棟の建設は、2022年度着工予定でしたが、未だ工事は始まっていません。その理由と今後の整備スケジュールについて、まずお聞きします。
現状は、1棟の解体を残し、すべて更地になっているだけでなく放置されています。そのため夜は暗く安全上の問題と同時に、残っている1棟に近い24号棟、35号棟、46号棟では、カラスやハトによる被害がひどく、「エレベーター入り口のふんがひどい」「べランダに洗濯ものが干せない」「カラスが自転車のサドル、前かごのビニールを破っている」などの苦情が出されています。住環境を守るためにも、街路灯の設置、カラスやハトの被害防止対策が必要と思うがどうか。
高砂駅高架のために車庫の跡地移転が検討課題とされています。高砂駅高架は、地域住民の悲願でもあり早期実現に向けて力を合わせるのは当然ですが、事業着手の目処がたつまでの間、暫定的にグランドゴルフ、野球、サッカー、ドッグランなどで活用できるようにすれば、既存の公園利用も合わせて幅が広がり、団地周辺も賑やかになると思うがどうか。
団地内の郵便局の存続を求める声が上がっています。団地周辺の郵便局は高砂5丁目と細田3丁目だけで、直線にすれば団地からの距離は2か所ともほぼ同じです。高砂駅前のスーパーにも行けない高齢者が多くいるなかで、さらに郵便局がなくなれば、日常生活は成り立ちません。元々、団地内には診療所、歯医者、八百屋などもあり大変便利であったにもかかわらず、建替えだということでなくなってしまいました。その建替えが遅々として進まず、今度は郵便局もなくなってしまうのかという不安と怒りがあります。郵便局を団地内に残す手立てを住民に示すべきと思うがどうか。
高齢化が進む中、「病院に行くにも、買い物に行くにもタクシーではとても無理」などバス運行の要望がたくさんでています。団地周辺は、循環バスの検討10路線の一つにもなっていますが、振り返れば26年前の交通アクセス改善調査で交通不便地域としたにもかかわらず、未だ何も変わらないのは行政の怠慢です。区内の交通格差をなくし、日常生活をささえ、社会参加を促すことが行政の仕事であり、小菅地域を運行する乗り合いタクシー「さくら」のような運行形態を検討すべきと思うがどうか。
建替え跡地に特別養護老人ホームの整備を求める声は、1万筆を超える署名に現れ、区長自身も区民と区長の意見交換会で特別養護老人ホームの整備について区民に約束しました。区内には依然として待機者が1000人以上います。厚労省の調査では、ショートスティの長期利用が年々増え、その理由は「要介護3以上の利用者で特別養護老人ホームの入所待機のため」が7割です。
一方、ベッドの空きがあることを理由に特別養護老人ホームの整備を否定する声があります。そのため特別養護老人ホームという施設名を使わず福祉施設などあいまいな言葉で区長の公約を否定する答弁が目立ちます。改めて、特別養護老人ホームの整備について区長は明言すべきと思うがどうか。
ベッドが空くのは、介護職員の不足や利用料が高いことが最大の原因です。区として介護職員の処遇改善や利用料の独自減免などを検討すべきです。区長の答弁を求めます。
以上で質問を終わりますが、答弁いかんによっては再質問することを表明しておきます。