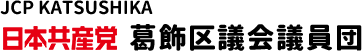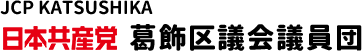通告にもとづき日本共産党葛飾区議団を代表して一般質問を行います。
まず区長の政治資金パーティーについてです。
区長は、所信表明で「依然として物価高が継続しており、区民生活にも大きな影響を与えている」と述べながら、国政でも都政でも大問題になっている政治資金パーティーを、3月19日に6千円会費、飲食なしで開催すると案内をだしています。やることが違うのではありませんか。
会費収入は、政治資金となるや否や課税されない収入となります。これが政治不信の原因となるのです。ですから先の総選挙では、政治資金パーティーに端を発した裏金事件に対して、物価高騰に苦しむ国民の怒りが沸騰したのです。パーティー開催は、区民の神経をさかなでするものといわなければなりません。しかも議会中にあえて開催するのは、神経を疑います。
昨日の暮らしや営業を応援するための提案をしたわが党の代表質問に対しても極めて後ろ向きな答弁ばかりでした。区民の暮らしよりパーティーですか。政治資金パーティーは自粛すべきです。区長の答弁を求めます。
次に、物価高騰緊急対策支援金、防災対策について伺います。
今、私たち日本共産党は、暮らしのアンケートに取り組んでいますが、その中で、「圧迫骨折に続き、乳がんで全摘手術を受け、現在、紙おむつをして要介護1です。紙おむつは要介護2以上で、私が受けたいと思う介護サービスは受けられない。病院に行くにもタクシー代がかかる」「主食や栄養がある米や玉子が上がるのはきつい」「野菜など、とにかく高いのは何とかならないか」など、切実な声が寄せられています。暮らしに安心とゆとりをつくるために、身近な区政の役割が問われていることを痛感します。
2月1日から申請受付が始まった事業者への緊急対策支援金についても、事業者を訪ねていますが、「売上が減っていても、代金に上乗せできない」「閉店した後も魚の鮮度を保つために電気は消せないので電気代が大変」「仕入れに行くのが怖い」という中で支援金は大変助かるという歓迎の声とともに、「知らなかった」「うちみたいな小さいところでもいいのか」など、せっかくの支援金を知らない事業者もいました。
本来なら中小企業の拠点となるテクノプラザかつしかが細かく発信し、問い合わせにも親身になって応じることが必要です。今回3回目の実施ですので、回を重ねるごとに手続きを簡素化するなどの工夫が必要だと思います。
事業者にダイレクトにお知らせし、漏れなく申請し、暮らしと営業に役立ててもらうためにも、悉皆調査を実施し、4回目につなげるべきと思うがどうか。
テクノプラザかつしかへ問い合わせをしたら、コールセンターに問い合わせるようにと言われた事業者がいました。中小企業の拠点にふさわしく、テクノプラザかつしかに支援金の窓口を開設し、事業者からの問い合わせには親身になって応えるべきと思うがどうか。
事業所の実態調査なしに生きた支援策はでてきません。やはり悉皆調査で地域経済の現状把握につなげ、事業者、関係団体、区職員などの話し合いの場を設け、地域経済の好循環のためには何が必要なのか、具体的な方策を検討するためのイニシアチブを発揮するのがテクノプラザかつしかの役割だと思うがどうか。
災害から区民の命と財産を守ることも区政の重要課題です。区世論調査で区政に力をいれてほしいことの第一位は防災対策でした。
能登半島地震では、災害関連死が直接死を上回っています。減災対策と災害後の対策が重要であることがわかります。
来年度予算案では、耐震改修や液状化対策の拡充などが盛り込まれ、感震ブレーカーの無償配布も継続するとしています。
感震ブレーカーの無償配布は重要ですが、地域によっては不合理なところもあります。たとえば、高砂4丁目は、都営住宅が大半であるため、火災危険度ランク1になり対象外です。しかし、4丁目の一部には、40軒ほどの密集した住宅もあります。区内全体を俯瞰して柔軟に対応すべきと思うがどうか。
阪神淡路大震災から30年経っていながら、体育館での雑魚寝状態の避難所のあり方が問われています。
災害時要支援者のためのテント177基を購入したといいますが、本区の防災計画では、第一順位の避難所の最大収容人員は11万2千人となっており、全く足りません。被災者の権利と被災者支援の最低基準を定めた国際基準であるスフィア基準では、本区の収容人員29,918人となっています。プライバシー保護の観点から、少なくともスフィア基準に沿って各避難所で世帯ごとに使用できるテントを計画的に確保していくべきと思うがどうか。
一般社団法人避難所・避難生活学会は、発災時から48時間以内に清潔で快適なトイレのT、温かい食事を提供できるキッチンのK、段ボールなどのベッドのBを避難所に整える「TKB48」を提案しています。発災してからではなく、日ごろからの備えが不可欠です。どこの避難所でも命と尊厳が守られる環境のためにも、段ボールベッドの計画的な確保やトイレトレーラー、キッチンカーの確保も重要と思うがどうか。
また停電時でも正確な情報がとれるよう防災ラジオを区民に配布すべきと思うがどうか。
次に学童保育クラブについて伺います。
学童保育クラブは、共働き・一人親の小学生の放課後生活を継続的に保障することを通じて、親の仕事と子育ての両立を保障する事業です。年間278日、1650時間にも及ぶ家庭に代わる毎日の「生活の場」であり、成長期にある子どもたちに安全で安心な生活を保障することが学童保育クラブの基本的な役割です。
本区では、待機児童を対象にした緊急対策として「かつしかプラス」を昨年から実施していますが、本質的な解決にはなりません。なぜなら児童福祉施設に位置付けられた学童保育クラブではないからです。そのため、プールの更衣室、机やロッカーなどが置いてある学校の空き教室などを使い、保育のための専用室やおやつはありません。平日19時まで、土曜日も利用できる見守りで、その点ではワクチャレと同様ですので無料は当然です。にもかわらず、「かつしかプラス」の利用者120人を除外し、待機児童を383人としていることは問題です。
来年度は、この「かつしかプラス」の実施校を8校に拡大するとしていますが、いくら増やしても待機児解消にはなりません。
そこで「かつしかプラス」を待機児童を対象にした緊急対策というなら、保育の質を担保するために、学童保育クラブと同様に専門職員を配置するとともに、実施校の周辺に適地を確保し、学童保育クラブを緊急整備することが必要と思うがどうか。
第二上小松学童保育クラブは、老朽化のために廃止するとしていますが、不足しているのに廃止はあり得ませんし、「かつしかプラス」に変えるのは本末転倒です。現在地で建替え可能であれば区の責任で建替えをするか、周辺に緊急整備をすべきと思うがどうか。
杉並区は、「どこにも居場所がないと感じる子どもが生じないよう、身近な地域に選択可能な居場所を用意していく」と述べ「児童館全館廃止計画」を撤回し、「児童館の存続・増設・機能強化」の計画を発表しました。
本区の場合は、児童館と公立学童保育クラブの全廃を打ち出し、子どもの居場所を減らし、学童保育クラブの待機児解消どころか、待機児を増やしてきました。まさに青木区政の失政によって子どもたちの生活の場が奪われてきたと言わざるを得ません。
学童保育クラブの待機児解消のためには、2つの取り組みが必要です。
一つは、緊急増設です。待機児童がいる地域には、活用できるすべての施設を利用して、公立学童保育クラブとして開設すべきです。
今一つは、人材確保です。学童保育クラブ職員は、非正規の不安定雇用が多く、全産業のなかで介護や保育と同様に極めて低い水準にあります。政府も学童保育指導員の処遇改善を置き去りにしていることも問題です。専門性の高い学童保育指導員について、区独自に抜本的な賃上げを行い、人材を確保すべきです。答弁を求めます。
学童保育クラブの所管を公立は子育て支援部、私立は教育委員会と分けていますが、保育の観点から子育て支援部に一本化すべきと思うがどうか。
区教委が実施した3回のアンケートの結果は、昨年の広報かつしか8月15日号1面トップの「安全、安心、楽しく、充実の水泳授業」とは裏腹の結果でした。今年度に実施した教員のアンケートは回答の仕方を変えていますので比較できませんが、子どもへのアンケートでは「楽しかったか」「コーチは良かったか」は、いずれも否定的な回答が増えました。子どもに対して、「今後も続けたいか」の項目を2回目から外したのは、子どもの意見表明権について「子どもの意見を聞かなければならないという解釈はできない」との教育長の間違った認識があることを指摘しなければなりません。
泳力別のグループ分けについて、技術力だけでなく、思考力、仲間との学びあい、伝えあいが必要という学習指導要領との関係で問題視する声、子どもへのハラスメントの指摘もありました。今年度も「低学年の学習指導要領の内容と指導自公があっていない」「指導は担任ではなくプールの指導員が行っている。担任は児童の観察、記録、補助を担っている」との意見があり,教員が直接指導していないことが改めて明らかになりました。
江戸川区は新たな水泳指導の方針案を示していますが、中学校改築時に屋内温水プールを整備し、3校~4校の近隣小学校が使い移動の負担を最小限にする、授業の評価は教員が行うために指導は教員が行うとしています。本区の水泳指導の民間委託での問題点を把握した当然の結果です。
教育委員会は、足元で起きている問題を直視すべきです。
まず移動の負担とバスの配車問題です。
移動の時間により、その後の授業、休み時間に影響が出ていることは否定できません。特にバスの配車は非常に深刻な事態になっています。
今年度は、入札不調が続き京成2社による10校分以外の13校分は随意契約となりました。この契約は、バスを配車することの契約であり、契約バス会社の自社バスでなくても良いとなっています。たとえば京成バスが落札をしても、他のバス会社に依頼することも可能であり、依頼した場合、どんな契約になっているかは教育委員会もいっさい把握していません。子どもの安全に関わる問題でありながら極めて無責任です。
来年度から13校分を大手旅行代理店に、3年間の一括契約するとの庶務報告がありましたが、予算は初年度1億2700万円、1校当たり約1千万円です。京成バス2社は10校分を4500万円、1校当たり450万円です。当初、バスの配車は、1校当たり160万円としていましたが、大手旅行代理店では1校当たりが6倍になります。
運転手不足から配車が困難になればなるほど契約料が上がる危険性だけでなく、代理店からバス会社、そのバス会社から他のバス会社へ、2重3重にコストの中抜きが行われ、質と安全対策が後退する危険性もあります。そうならない保障はあるのか、具体的にお答えください。
子どもたちにとってより良い水泳指導になっていないことは、アンケートからも明らかです。にもかかわらず、当初の6倍にもなる費用をかけて実施することは、税金の使い方として区民の理解は得られないと思うがどうか。
さらに契約したバス事業者、大手旅行代理店によって安全誘導員の仕様書が違っています。誘導員をつけなくても良い契約、誘導員がバスに乗車して安全を確認する契約、乗車しない契約など、同じ安全対策であるなら、仕様書も同じでなければなりません。なぜ変えるのか、具体的に説明願います。
新たな屋内温水プールの整備についても問題があります。
水泳指導の民間委託を導入する際、教育長は、民間施設の受け入れ不足の事態は、現時点で問題ないと強弁していましたが、何の根拠もない場当たり的な答弁であったことは、区立屋内温水プールを3か所整備することになったことで明らかになりました。
新宿地域、お花茶屋地域での説明会では、反対意見が続出しただけでなく、反対意見を隠して「主な意見」として地域住民にチラシでお知らせしたことは教育委員会の隠蔽体質が現れています。
来年度予算案では、新宿地域における整備費が債務負担行為も合わせて約30億円が計上されています。
バス配車が今後どうなるのかわからない中で、30校の水泳授業を3か所に集中させるプール建設も、税金の使い方としてどうなのかが問われます。
学校教育施設として整備するというなら、学校内に整備することを最優先に考え、学校が使わないときは一般開放することで学校がスポーツ拠点にもなるようにすべきと思うがどうか。
整備費について、加温式の屋内プールであれば、約5億円で整備できます。仮に30億円の3か所分、90億円あれば、改築校にバランスよく18校整備することができ、当面、近隣校も活用すれば移動の負担を最小限に減らすことができます。こういう方向に転換すべきと思うがどうか。
双葉中学校はグランドが狭く、改築を求める声が大きくなっています。改築校に選定し、屋内温水プールを整備すれば、現在のプール敷地、新たに取得した敷地をグラウンドとして活用することができ、生徒にとても地域にとってもプラスになると思うがどうか。
柴又小と東柴又小の統合は、地域住民のほとんどが知らないまま、また統合を認めなければ桜道中学校の改築はしない、などの脅しで統合を決めたことは問題です。しかし東柴又小学校が改築校となったからには、地域住民との約束は守らなければなりません。東柴又小学校のプールは、鎌倉公園プールを廃止した際、地域に対して一般開放を約束し、それを実施している学校プールです。したがって東柴又小の改築の際には屋内温水プールを整備し、学校でも地域でも活用できるようにするのは当然だと思うがどうか。
学校プールと学校外プールとの格差が放置されています。
熱中症対策は、来年度、やっと学校プールへの遮光ネットを設置するとしていますが、プールサイド1辺のみの中途半端なものです。学校外プールでのバスには1校当たり1千万円かけながら、遮光ネットは、1校当たりわずか60万円しか使わない。恥ずかしくありませんか。
遮光ネットは、プール全体を覆うものにすべきです。もし覆わなくても熱中症対策になるというのであれば、屋内温水プールでなくてもいいという事になると思いますが、教育長の答弁を求めます。
プールサイドなど床面の温度上昇を抑えるためのタイル、ゴムチップ舗装、シートなども検討すべきです。
学校プールでは、水質管理の負担があり、インストラクターの配置もなく、教員の負担軽減は後回しになっています。改善すべきです。答弁を求めます。
学校外プール活用校に対して、夏季休業中の水泳指導を実施させないことは問題です。
夏季休業中の水泳指導について区教委は、学校の任意だと言っていますが、実際には、学校外プール活用校は、授業1回分増やしたことを理由に実施させないのが実態です。学校プールでは今年度、28校が実施しています。かつしか教育プランについて学識経験者から、夏休みのプール開放は体験学習として重要との指摘がありました。家庭の経済状況に応じて夏季休業中の水泳体験ができない状況があってはなりません。学校プールを活用し、社会教育として指導員を配置して実施すれば、1校当たり500万円ほどの財源で可能であり、教員の負担なくできると思うがどうか。
バスでの移動のない水泳指導に切り替えれば、年間1億7200万円の財源を子どもたちにとってより良い使い方に変えることができることを強調しておきたいと思います。
次にバルサアカデミィー葛飾校について伺います。
バルサアカデミー葛飾校は、サッカーの強豪チームFCバルセロナを冠したサッカースクールですが、1月23日の文教委員会で、運営主体であった一般財団法人キッズチャレンジ未来、以下、キッズチャレンジとさせていただきますが、このキッズチャレンジとの協定を今年度末をもって終了することで合意したと庶務報告がありました。しかし、キッズチャレンジとの協定は、決してあいまいにできない問題があります。
その一つは、キッズチャレンジは、バルサアカデミィー葛飾校の事業をR4年度に4900万円で株式会社アメージングスポーツラボジャパン、以下アメージングとさせていただきますが、このアメージングに譲渡しています。区は、事業譲渡の事実を把握していませんでした。
さらに昨年9月2日、キッズチャレンジ、アメージング、生涯スポーツ課の3者の打ち合わせでは、事業名の変更、優先利用できるグラウンドに水元総合スポーツセンター多目的広場の追加、キッズチャレンジとアメージングの共同運営に、すでに変更されていることから協定を見直す話合いがされています。
事業譲渡も、事業名の変更も、運営者の変更も、区が知らない間にされており、協定違反です。教育委員会はその認識はありますか。また抗議、注意したのか、相手から謝罪等の文書が提出されたのか。答弁を求めます。
9月2日の内容は、勝手に変更していたアメージング、キッズチャレンジの代表2人とも見直しは「やったほうがいい」「私も同じ考え」とのべ、区は「ご理解いただきありがとうございます」と協定違反の相手に対して、おもねる態度です。どうしてこういう関係になっているのか、やはりあいまいにすべきではありません。
水元総合スポーツセンター多目的広場の追加は、キッズチャレンジから依頼があったとのことですが、なぜ協定の見直しをせずに放置してきたのか、説明願います。東金町運動場の使用承認は青木区長が出していますが、そういう手続きも不要な関係になっていたのですか。
いつのまにか事業譲渡していた、ありえない話です。どんな理由で譲渡したのか、4900万円の根拠は何か、文教委員会では、譲渡契約書、内訳、赤字補てんしたことがわかる資料を要求しましたが、「依頼中」のままです。2月19日の文教委員会でその後のことを聞きましたら、「提出する」とも「提出しない」とも返事がないとのことですが、どうなったのか。答弁を求めます。
今一つは、そもそもバルサアカデミィー葛飾校は、赤字事業でありながら、キッズチャレンジは、毎年多額の接待費を支出しており、赤字体質を改善しようという努力がみられません。月謝を不正に使っていたのではないか、と疑われても仕方がありません。
昨年9月2日の3者の打ち合わせでは、アメージングの社長から「キッズチャレンジが月謝を集めていたらお金の流れが見えにくくなる」との発言がありました。その意味を確認したところ、「キャッシュフローが回らない原因がわからない」とのことでした。その原因がわからないままであるならば、事業継続の見通しがないと思うがどうか。
2月19日の文教委員会では、アメージングから今後の運営についての提案があったことが報告されましたが、営利企業であるアメージングが運営主体となれば、営利目的であり、グラウンドの優先利用はありえないと思うがどうか。
キッズチャレンジ設立時の発起人の役員に当時の副区長が派遣されており、その後も平成27年8月31日まで評議員となっています。一定の権限を持つ職員を派遣し、設立に関わっており、区としての説明責任があります。
なぜ葛飾校だけが、キッズチャレンジという団体が必要だったのか、グラウンドの優先利用、管理棟の独占使用をさせるためにどのような協議がされてきたのか、副区長を派遣するにあたって、それまで双方の事務方ではどのような協議がされてきたのか、会議録等も含めて区長は説明責任を果たすべきと思うがどうか。
次に、高砂団地建替え跡地等のまちづくりについて伺います
高砂団地建替え跡地への特別養護老人ホームの整備は、青木区長が「区民と区長の意見交換会」の場で約束されたもので、区民に対する公約です。ところが昨年の第2回定例会では、「特別養護老人ホームやその他の施設を含め、今後必要となる福祉施設を検討し、整備する」との答弁でした。「今後必要となる福祉施設を検討」するという答弁は、区長の公約を後退させる印象を与えかねません。改めて、区長自身の言葉で、区民との公約を守るのかどうか明確にしていただきたいと思います。
水元公園へのスケボー広場の整備は、区長が先頭に立つことによって、実現の方向へ向かっていますが、高砂団地建替え跡地への特別養護老人ホームの整備についても、同様の立場で臨み、整備スケジュール等を住民に示すべきと思いますがいかがですか。
私が高砂団地建替え跡地への特別養護老人ホームの整備にこだわるのは、1万筆を超える整備を求める署名に寄せられた地域の声、待ち続けている地域の声、残念ながら亡くなった方々の家族の声があるからです。
特別養護老人ホームの待機者は、現在、1000人を超えています。区が実施した世論調査では「整備・充実が必要な施設」の第1位は特別養護老人ホームです。ところが5年以上にわたって整備計画がありません。区民の切実な願いに応え、待機者解消に見合った整備計画を持つべきと思うがどうか。
団地内にある郵便局の存続を求める声は切実です。創出用地へ移設することを都に強く要請すべきと思うがどうか。
高砂団地周辺は、27年前から交通不便地域となっていますが、未だ解消されていません。小菅地域を運行する乗り合いタクシーさくら、東立石地域を運行するグリーンスローモビリティなどを参考にして、区が交通格差を解消するために直接責任をもつ運行形態でただちに解消すべきと思うがどうか。
以上で私の質問を終わります。答弁いかんによっては再質問を行うことを表明しておきます。