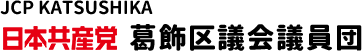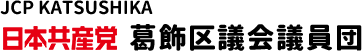日本共産党葛飾区議団を代表して一般質問を行います。
今月、葛飾区内でも闇バイト事件が2件続きました。高齢者を狙う「オレオレ詐欺」から、手口が巧妙になり「特殊詐欺」へ、そして今、お金ほしさに軽い気持ちで「闇バイト」に手を染める若者たちが社会問題になっています。その手口は、言葉の軽さとは裏腹に凶悪化し、家に押し入り暴力をふるい、金品を奪う強盗や殺人事件になっています。
こうした事件が後を絶たないのは、経済が低迷し、賃金も上がらず、さらに物価高騰が格差と貧困を広げ、まじめに働いても生活に不安を抱える社会になっていることと無関係ではありません。
そのことは、先の総選挙で、まともな経済対策がない一方、派閥パーティの裏金キックバック問題、非公認となった候補者にも2000万円を党本部から支出する「裏公認」ともとれることに怒りが爆発し、自民・公明が過半数割れという結果になって現れました。
選挙では賃上げなどが争点になりました。賃上げの問題も争点となり、今でも、「103万円の壁」が議論されていますが、「保険料の壁」の問題もあり、総合的な判断が必要です。
物価上昇に合わせて課税最低限を上げることは当然ですが、最低賃金1500円への引き上げ、低所得者の社会保険料の軽減で、税金や保険料を引いても、手取りが減らないようにすることや学生が100万円働かないと学業を続けられないことが異常であり、授業料の無償化や給付型奨学金の拡充なども合わせて考えていく必要があります。
福祉を向上させ区民の暮らしを守るのは自治体の使命であり、そのためには国に対して声をあげつつ、区独自の対策が必要です。
まずは景気回復の特効薬は何と言っても消費税の減税です。岸田政権の定額減税などの小手先の減税では何も変わりません。消費税の減税、インボイスの中止を国に求めるべきです。
マイナ保険証について、紙の保険証存続の声が強まっています。そもそもマイナカードは任意であり強制すべきものではありません。現在の運転免許証は選択できます。マイナ保険証も同様の対応すべきであり、紙の保険証は存続させるよう国に求めるべきです。
区としてもやるべきことは、国民健康保険、後期高齢者医療の資格確認証をマイナ保険証の登録有無に限らず被保険者全員に交付すべきです。10月28日からマイナ保険証の登録解除ができるようになっています。多くの自治体が、28日以前からどの窓口に行けばいいのか、必要な書類などを周知していますが、本区では、今月11日やっとホームページ上に「12月2日以降、国保年金課窓口で受け付ける」と掲載しました。しかも、広報かつしかでは、登録解除については未だ一言も触れていません。マイナ保険証の登録解除は、登録者に個別に周知徹底すべきと思うがどうか。
物価高騰に対応するため、区として思い切って具体化することを求めます。
1、 本区における会計年度任用職員の男女比率は女性が8割です。その時給が23区平均を下回っていることは、雇用形態における男女差別であり、時給の抜本的な引上げること。
2、 国は低所得世帯について3万円の給付を検討しています。対象外となる世帯に本区独自の給付金の検討。
- 学校給食や修学旅行等の無償化は、私立学校に通う区民の児童生徒にも相当分の支援。
- 国民健康保険の就学前の子ども均等割り保険料の免除。
- 学童保育クラブ使用料の無償化。
- 介護保険利用料の独自減免
- 奨学金貸付に対応する返済支援と給付型の創設
- 大学進学のための給付型奨学金の創設
- 低所得世帯のエアコン設置助成の再開と電気代助成、答弁を求めます。
中小企業対策では、杉並区が実施した中小企業への電気・ガス代の一部助成は、使用料を4段階に分けて3万円~15万円の助成をするもので、5か月間で5700件を超える実績となっています。世田谷区では、訪問介護事業所の介護報酬改定による不足分を補てんすることを目的に支援給付金を開始しています。物価高騰や介護報酬減で営業が厳しくなる中、これまで実施してきた個人・法人事業主への支援金や介護事業者への報酬減を補う支援金を実施すべきと思うがどうか。
今年も1か月余となった中、年末年始は相談窓口を拡大する必要があります。区役所が閉庁する前の12月23日~27日まで、区役所前広場や区内JR駅での街頭での生活相談とともに、食料支援を実施してはどうか。
閉庁期間である12月28日~1月5日まで、相談所の開設が必要であり、休日窓口はもちろん期日前投票所となる庁舎1階スペースや区民事務所で相談窓口を開設し、食料支援や住まいの緊急対応ができるようにすべきと思うがどうか。こうした年末年始の相談窓口を早くから周知すべきと思うがどうか。
次に、障害のある人とその親のライフステージに合わせた支援体制についてです。
今年は日本が2014年に「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」を目的とした障害者権利条約を批准して10年目の年であり、7月には旧優生保護法に対し、違憲の最高裁判決が出ました。障害者も普通に暮らしたいという願いを長年にわたり阻害してきた立法と行政は真摯に反省しなければなりません。
国連・障害者権利委員会は2022年、日本政府に対し障害者権利条約28条「相当な生活水準及び社会的な保障」と、19条「自立した生活及び地域社会への包容」の是正を求めています。これは国内の障害者のライフステージに合った暮らしの支援が遅れていることの指摘であり、障害者施策推進計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画を今年度更新した本区においても、国連の指摘を意識し、推進すべきです。
障害のある人たちを支援する事業所の全国組織である「きょうされん」が行った全国アンケートが今年、集計され、障害者が尊厳のある暮らしからかけ離れている実態を示しました。
5891の有効回答によると、生活保護を受給する障害のある人は全体の11.5%。一方で国民全体の生活保護受給率は1.63%であり、障害のある人の受給率は全体の7倍以上、加齢に伴い受給率が上がっていく傾向です。
また障害のある人の主な収入は、基礎年金1級、基礎年金2級、がほとんどであり、生活保護による補償を除いて、障害基礎年金・厚生年金・障害手当・給料・工賃などすべてを含む本人の月額収入を12か月で積算した年収を見ると、50
万1円以上100万円以下が36.4%と最も多く、次いで100万1円以上125万円以下が33%という結果であり、アンケート調査の回答者の78.6%が、厚生労働省の国民基礎調査で示された相対的貧困とされる年収127万円以下の生活しています。
回答によると、多くの障害者が50才代前半まで家族と同居、特に親に依存した生活を送っており、年収が低いほど親との同居の割合が高くなるという特徴があります。年老いた兄弟や老齢の親がいつまでも障害のある人と暮らすには限界があります。
そんな状況で株式会社恵が経営していたグループホームの不正受給問題が全国的に衝撃を与えており、障害者の暮らしの実態調査と施策が必要です。そこで質問します。
①本区では障害者の収入や家族介護者の有無などの生活実態の調査を行っているのか。また行っていないのであれば、すぐに取り組む必要があると思うがどうか。さらに調査に基づき貧困の解消に取り組むべきであるがどうか。
②障害者就労支援センターの利用登録者数が年々増えているが、本人が希望する就労に結び付くのは難しい実態がり、本区のチャレンジ雇用の新規募集を停止せず、障害者の就労を促進していくべきではないか。またオフィスサポーターも法定雇用率にとらわれずに増やして、就労機会を創出してはどうか。
③三障害の方への移動支援の除外項目と利用時間を見直し、より利用しやすくし、外出の機会の保障をすべきではないか。
④身体・知的障害者の巡回入浴サービスを週に1度(年52回)しか提供しないのは健康で文化的な生活とは言えず、生活の質を高めるために回数を増やすべきと思うがどうか。
⑤今年度行った障害福祉サービス事業者の運営を直撃する報酬改悪で、収益悪化や離職等による撤退を防ぐための施策を講じているのか。
⑥物価高騰が止まらない中で、福祉サービスの利用料の減額、無償化することで、経済的負担の軽減を図るべきではないか。
私は大分市の障害者とその親を支える取り組みを視察して来ました。
大分市の取り組みのモデルは平成25年に別府市で先駆的に成立した通称「ともに生きる条例」です。別府市の条例は差別や虐待への解消の取り組みの他、障害のある人の生活を支え親なきあと、どう生活をしていくかという不安に寄り添った取り組みです。
別府市の取り組みは大分県下に広がり、障害者の保護者自身が高齢や自分の死などの理由で支援を続けられなくなった後の不安に対して、「親なきあと相談室」の相談員が総合的な相談を受け、困りごとが発生する前に、専門家や関係機関による相談窓口事業を行っています。大分県と地元の社会福祉事業団が連携し、令和元年から3年にかけ相談員養成研修講座を行い、134名以上の「親なきあと相談員」を養成、また、事業団の相談員を各市町村に派遣し「親なきあと相談会」の開催の援助を行っています。
事業団における親なきあと相談件数は、家族・障害者本人・福祉関係者含め開設から昨年10月までに215件の実績を上げており、当事者とその親の将来の不安解消につなげているとともに、この取り組みで将来地域に必要な社会資源の姿の展望が見えるという利点もあります。そこで質問します。
①本区において、基幹相談支援センターや、「相談」機能を持つ拠点機能事務所で受けた親なきあと相談は何件あるか。また親なきあと相談を担える相談員は何人いるのか。
②大分県では障害のある子を持つ親が、親なきあとに支援者に知っておいて欲しいことをまとめておく「エンディングノート」を独自に作成し、配布しています。本区でも取り入れることで、スムーズな支援につながると思うがどうか。
③本区でも親なきあとに特化した相談日や、各地域での相談会を行えば不安の解消や、ニーズの把握につながると思うが、実施してはどうか。
④親なきあとの暮らしに備え、早い段階から将来の自立した生活の訓練が重要だが、本区の宿泊型自立訓練施設は足りているのか。また各施設の利用者が老齢期になり、その先の支援の行先も人手も足りないと聞くが、増やしていくべきではないか。
⑤三障害の手帳の所持者は増加傾向にあるが、今年4月においての交付数はいくらか。また手帳の所持者に対して、年齢や障害の度合いに応じて必要な支援が届いているか、区はどのように確認しているのか。
⑥家族介護者のレスパイト事業について、日数や利用条件を使いやすくするべきではないか。また、家族介護者が老齢になり日常生活に手助けが必要となった時に、親子で入居できる施設があれば障害者とその家族にとって安心に暮らす選択肢が増えると思うが、区営で施設を作る検討をしてはどうか。
次に、区内公共交通について質問します。
2019年に策定した本区の「公共交通網整備方針」は、区内の公共交通について、あたかも交通不便地域がないような認識でいることに問題があると、わが党は当初から指摘をしてきました。
なぜなら1998年の「交通アクセス改善調査報告書」では、公共交通不便地区として10地区をあげ、その対応案が示されていました。26年経過しても未だに解決されていない地区があるにもかかわらず「利用状況に大きな差異は見受けない」という方針では、公共交通を充実させることはできません。
私は大分市の公共交通の視察をしてきました。
大分市では、「民間の交通事業者が収益を確保できる形で公共交通を担う」という構造が難しくなってきているなかで、過疎地域に対して、多様な関係者が連携することで、「不便地域の解消を目指す」「バス代替交通の見直しで移動機関の確保を目指す」という方針を掲げて取り組みを強めています。
路線バスの一部ルートが休止されれば、代替としてジャンボタクシーによるコミュニティバスの運行、公共交通機関の利用が不便な地域は、最寄りの路線バスのバス停までワゴンタクシーの運行、3か所の過疎地域では、グリーンスローモビリティをタクシー事業者への委託で運行しています。
「不便地域の解消」という方針を掲げ、バス事業者やタクシー事業者と連携し、行政が主体となり過疎地域から中心街まで、面的な公共交通としてバス路線の構築を行なっています。
大分市の財政規模は本区と同規模ですが、公共交通には、3億円以上の財政支出をしており、考え方も取り組みも本区とは大きく異なります。
そこで質問します。
1998年の区「交通アクセス改善調査報告書」で交通不便地域とした10地区のうち、改善した地区、改善できていない地区は具体的にどこか。
「公共交通整備方針」では、区内には「公共交通の利用状況に大きな差異はない」として交通不便地域がないかのような認識となっているが、質すべきではないか、答弁を求めます。
交通は人権であり、住民の足を確保するためにも、以下のことを求めるものです。
1、「整備方針」で検討するとしている10路線で運行に至っていない路線については、地域乗合タクシー「さくら」の運行形態で実証実験を実施すべきと思うがどうか。
2、「レインボーかつしか」有70・72・73・74の対象地域でのアンケートの結果、西亀有地域についての検討が示されましたが、白鳥エリア、新宿エリアについても、具体的な検討が必要と思うがどうか。
3、2024問題は、もはや民間事業者だけで交通網を維持していくことはできないことがはっきりしています。日本バス協会は、2030年まで現状の路線維持のためには、運転手が36000人不足すると試算しています。フランスでもドイツでも地方公共交通の事業費に対する運賃収入は4割程度で、差額は国や自治体が補填しています。韓国では、サービス向上のため、バス事業者が「準公営化」され、収支の不足額は行政が補填しています。事業者の経営努力や運賃収入だけで持続可能な地域公共交通を実現することはできないからです。地域公共交通は、「公共サービス」という認識に立って、バス事業者への抜本的な財政支援を強めるべきと思うがどうか。
4、大分市のグリーンスローモビリティは、市が1台3000万円程の車両を3台購入し、一台の人件費、車両の管理費、保険など900万円でタクシー事業者に委託し、ています。行政が責任をもち、本区とは決定的な違いがあります。現在、実証実験しているグリースローモビリティについても、本区が主体となって運行することも検討してどうか。
5、大分市では、運転免許を持つ70歳以上、免許を返納した65歳以上は、専用の乗車証を見せれば、乗車料金の半額などでバスを利用することができる長寿応援バス事業があります。本区でも、高齢者の移動支援や社会参加という観点から検討してはどうか。
6、小田急電鉄では、2022年3月から子ども運賃は一律50円、京急電鉄は2023年10月から一律75円にしました。また、EU諸国では、国によって違いはありますが、公共交通の子ども料金は19歳まで無料や割引運賃が当たり前です。子ども料金の引き下げによって、大人の需要も喚起することができます。本区の子どもの権利条例は18歳までが子どもと定義としており、子どもの移動権の保障、子育て世代の負担軽減のためにも、子どもバス運賃を18歳まで無料にするなど事業者に求めてはどうか。
7、金町駅から葛飾区役所に行くには、亀有駅で乗り換えるか、青戸車庫から徒歩となります。大変不便であり利便性向上のためにも、直通でいける路線が必要と思うがどうか。
8、新小岩・金町間の新金01は未だ土日運行だけです。平日運行にも踏み出すべきと思うがどうか。
次に、立石駅北口再開発等の今後についてです。
前定例会で、2022年12月から2024年4月の総事業費が932億円から1185億円に253億円の増となりました。区は、「広報」も使い、何回も保留床価格は、242億円で新しい庁舎ができると繰り返し、全員協議会でも、それを前提にして「区役所の位置条例」を議決しました。しかし、この予定価格の変更は、その前提を覆すものです。
先の定例会で明らかになった3つの問題点を指摘します。
第1に、今後の事業費がいくらになるかわからない、その先は、ゼネコンの言いなりにならざるを得ないという問題です。
区の試算では、東棟の保留床の価格は、2030年には、380億円との予測ですが、この想定自体が甘いものです。江戸川区、北区、中野区の事例を具体的から、2倍近い事実を示し、葛飾だけがなぜ1.6倍で済むのかと質しましたが、明瞭な回答はありません。
しかも、前定例会中に急きょ開催された区議会議員協議会の資料では、参考データとして東棟の設備工事費の上昇率は、2022年と2025年建築工事請負契約締結時比で196.59%とすでに2倍になっています。最終「清算」時には、さらなる保留床の上昇は避けられないのではないか、答弁を求めます。
同時に、着目したのは、2022年12月から2024年4月比の物価上昇で工事費がどうなったのかという分析です。この分析は、特定業務代行者の建築工事・設備工事の検証ができたのは、36.5%に過ぎず、特に機械設備工事では、22.1%にすぎません。ほんの一部の検証でさえこれだけに工事費増となっているのですから、物価上昇を理由に、特定業務代行者が、さらに保留床価格を最終的に釣り上げらたら抵抗できるのか、答弁を求めます。
「駅前庁舎」には様々な変遷がありました。本館、新館を全部なくすことを前提にしましたが、事業が進まない苛立ちから、駅前移転を縮小し、新館を存続させる方向に転換しました。しかし、R5年の第3回定例会の総務委員会庶務報告で、新館の取り壊しの検討にまで、踏み込みました。
これは、現再開発方針を何があっても変更しない、つまり、後戻りはありえないという、これまた、特定業務代行者・ゼネコンいいなりの態度だと批判されても仕方ない態度ではないか。新館の活用方針は、堅持すべきと思うがどうか。
第2に、事業費の増加を税金で穴埋めしようとしている問題です。
前定例会では、事業費全体で253億円の増、そのうち、補助金で121億円賄い、さらに「公共施設管理者負担金」が39億円の増、加えて、東棟、西棟の庁舎を中心とする保留床の増加分が49億円です。したがって、事業費増253億円のうち209億円、率にして83%が税金によって賄われるということになります。
この再開発は民間事業ですが、「官製」事業だという姿が、ますます鮮明になっています。ここでいう「補助金」の増額も総務、決算各委員会や全協でも、満額支出の保障はなく、願望であることも明らかになりました。
結局、「補助金」もまた、税金であることに目をそらす無責任です。「補助金」が年度ごとに変わり、廃止予定のものもあること、「補助金」も血税であるという認識があるのか、答弁を求めます。
第3に、地方自治を破壊する「モラルハザード」ではないかという問題です。
どんな自治体でも庁舎を建設する場合には、国の補助金はありません。なぜなら、地方自治体は、国の下部組織ではなく、あくまでも対等な関係にあるからです。これは憲法の原則の一つが「地方自治」であることに起因するものです。
しかし今、国策として再開発を進め、補助金獲得のための悪用が広がっています。
「補助金」という税金投入で再開発を進め、新たな保留床をつくりだし、その保留床を異常に高い価格によって税金で取得する、このことは、税金の二重払いではないのか。
庁舎建設には国の補助金制度はないのに、再開発により補助金を得て庁舎建設を計画すること自体モラルハザードであると思うがどうか。
党区議団は、11/1~3まで、江東区で、土地区画整理・再開発全国研究集会に参加しました。そこでの発言、交流で、今日の再開発は、物価高騰という外的要因によって、「潮目」の変化がおこっていることでした。
現在、品川区や杉並区で再開発ラッシュが続く中、各地でそれに異を唱える戦いも進行している事例も紹介され、そこで繰り広げられている市民運動の交流も行われました。
品川区では、現在進行中の再開発が20ケ所あり、そのうち9つの再開発に係る地域住民が連絡会をつくり運動を交流しています。
品川区で進んでいる再開発は、新たな公共施設の建設を目的としたものではなく、そこにできるタワマンや、商業施設、ホテル、企業のビジネス街に「補助金」という名の税金が大量に支出されているという事例です。
これにはカラクリがあり、品川区やさいたま市では、副区長・市長には、国土交通省幹部が出向し、都心、副都心地区を中心にした再開発が進んでいます。
こうした仕組みが、都心、副都心等と周辺区との格差を拡大する原因になっている現状、国策として再開発推進・大企業奉仕の街づくりに多額の「補助金」を誘導する仕組みが作られていることについて区長はどう見ているのか、答弁を求めます。
私は、こうした自治体間格差を作り出しているこの仕組みの被害者は、葛飾区自身でもあるのではないか。これ自体が「地方自治」破壊ではないかと思います。
こうした現状を直視するのなら、庁舎建設のために、その「おこぼれ」=補助金を獲得のために汲々とし、「地方自治」破壊に加担するのではなく、再開発制度の見直しを世に問うことが、葛飾区民の代表として取るべき態度ではないかと思うがどうか。
葛飾区のモラルハザードの現状は、目を覆うばかりです。
いま、住民監査請求の後、住民訴訟として係争中の案件が4件あります。①児童相談所の定期借地権②私立保育園パート補助金の返還を求めない弁護士費用③立石駅周辺のエリアマネジメントの官製談合さえ疑われる案件④立石駅北口再開発の「権利変換に異議」をとなえる集団住民訴訟です。どの案件も係争中としてまともに答弁がなされませんので指摘しておくものです。
最後に、特定の「財団法人」を特別扱いしてきた区政のゆがみについてです。
11月14日に文教委員会で審議が行われた、営利企業の事業でありながら財団法人を隠れ蓑にして特別扱いをし、公共施設を使用させ、本来、入るべき収入を散逸させ、その他、説明がつかない税金投入が行われた問題です。
事実の解明のための調査、関与した特定の人物などが必要であり、区と教育委員会が全面的に協力すること、民間の団体、企業の事業だとはいえ、区と教育委員会自身が公共性のある事業として認めてきた事業であることを鑑み、必要な資料要求を行うとともに、当該団体、企業にも協力することを求めるべきと思うがどうか。