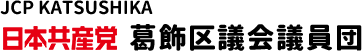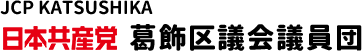区議団を代表して区政一般質問を行います。
物価高騰が区民生活を直撃しています日本共産党葛飾。先の参院選での国民の審判は、無為無策の政府与党に対する重大な審判となりました。
今やるべきことは、野党が掲げた消費税減税に道筋をつけることです。なぜなら、実質賃金が物価高騰においつかず、最新の「葛飾区の景況調査」でも不動産部門を除いて土砂降り状態です。
最も身近な自治体である葛飾区が、この現状からどう区民生活を守るために具体策を提案するのかがまさに問われています。
今定例会の補正予算は、そうした観点に立つ提案がありません。そこで、以下、質問します。
第1に、区民を守るための暑さ対策です。
まず、猛暑が続き、熱中症で搬送された方は、今年過去最高を更新し、8300名を超え、亡くなった方も毎年増え続け、10年前の二倍、今年は、100名を超しています。8/26付都政新法によれば、熱中症死亡例の44.9%がエアコンを設置しているのに使用していない、電気代がかかるからと我慢している方がいかに多いことを示すものです。エアコン使用は生命にかかわる問題といって過言ではなく、電気代助成は喫緊の課題であり電気代を助成すべきです。また、生活保護受給者は、夏季加算を設けるべきではないのか。
二つ目に、エアコン設置助成の拡大です。東京都がエアコン設置助成を開始します。本区の制度との違いは、所得制限がないことです。北区は、都の東京ゼロエミポイント拡充に加え、区独自で4万円を上乗せ、非課税世帯はさらに3万円の上乗せで、都と区を合わせれば最大15万円の補助になります。本区でも区独自に上乗せを検討してはどうか。また、本区が実施しているエアコン購入費助成を、全ての区民が利用できるよう対象世帯を広げるべきではないのか。
三つ目に、一人ぐらし高齢者毎日訪問事業です。高齢者に対し、配達員が一声かけて配達し、安否の確認を行うことは、熱中症予防にとっても極めて重要です。この制度を拡充し無料で届けてはどうか。
四つ目に、学校プール授業の改善も必要です。一校あたり60万円ほどの予算が組まれた暑さ対策ですが、あまりに粗末すぎます。暑さから命を守る立場で、学校プールの日よけを開閉式シェードや固定テント屋根等とすべきと思うがどうか。
第2に、物価高騰から区民のくらし・営業対策です。
新米の流通が始まりましたが、米価の高騰は区民のくらしを脅かしています。備蓄米がようやく流通し、店頭に並んでいますが、いずれなくなります。失政のツケがここにも及んでいます。これまで、東京都が行ったお米等のクーポン、昨年は、品川区が、子どものいる世帯にまた、豊島区もコメを配布しました。
そこで、物価高騰に苦しむ区民生活の下支えをするため区が「お米券」を配布し、少しでも負担軽減をすべきと思うがどうか。
二つ目に、中小企業対策です。
物価高騰緊急対策支援金を3回実施しました。事業者にとって、物価高騰が続くなか商売を続けるのが困難となっています。早急な実施と、個人事業10万円、法人事業20万円、給付額の増額をしてはどうか。
また、経済の好循環を生み出すカギは、物価高騰を上回る賃上げです。群馬・太田市では、県と連携し、支援金支給を受けた市内事業者に対して、賃金5%の引き上げを行い、県5万円、市2万円、合わせて一人あたり7万円を支給しています。渋川市でも、県の制度を活用し、一人あたり5万円の支援金を支給していますが、1万円上乗せ支援をしています。給付の仕方は様々ですが、物価高騰のなか、区内中小事業者に対して支援を行い、賃金の底上げしてはどうか。
第3に、子育て支援について質問です。
義務教育は無償化の立場で、一貫して学校給食の無償化、修学旅行の無償化等を実現しました。本区こそ、その流れを止めず、新たな事業を進めるべきです。
足立区では、来年4月以降に、所得制限なしで、小中学校へ入学する児童・生徒一人あたり10万円の入学準備金を支給します。本区でも義務教育を進めるうえでも、就学援助と同じように、10万円の入学祝い金の支給を検討してはどうか。
また、学校に通うために必要な交通費である通学定期代も負担軽減すべきです。中高校生、通学定期購入代金に対し助成すべきではないのか。
2つ目に、本区最大の問題は、学童保育クラブの待機児が最大になっており、その解決が急務の課題になっています。
令和7年度4月時点の学童保育クラブ待機児童数は、550人です。しかし、待機児童数から、かつしかプラス利用者251人の児童を待機児から除外することは、公的責任を投げ捨てるもの以外の何物でもなく、かつしかプラスは、学童保育クラブではありません。待機児童解消に見合った、学童保育クラブの増設をすべきです。
子育て世帯の経済的負担軽減ということで、給食無償化を実施してきました。学童保育クラブ使用料の無償化、おやつの無償化に踏み出すべきではないのか。
3つ目に、延長保育の利用料は、無償化の対象外となっています。本区として、充実した子育て支援制度のため、他の自治体よりも先駆けて、延長保育の利用料を無償化し、完全保育の無償化すべきではないのか。
4つ目に、高等教育に対する支援です。
子育て支援策として、18才までの医療費無料化、高校授業料の支援などが進められてきましたが、高等教育支援策が立ち遅れています。教育を受ける権利は、経済的に制約されてはなりません。
日本学生支援機構の給付型奨学金を受けている学生を対象とした調査では、アルバイトなしでは大学に通えない。物価高で「家計が苦しくなった」が91%で、全体の9割以上が満足な食事が取れていません。アルバイトと奨学金で生活している学生が55%で学業と就労の間で苦悩している実態が明らかになっており、一日に1食という学生も増えています。奨学生の半分が平均300万円以上借りており、借金を背負うこと自体問題です。
足立区の区独自の返済不要の奨学金制度に続き、品川区は、2025年2月、医療・理系の学部に進学する大学生への返済不要の給付型奨学金制度を創設しました。本区でも、思い切って若者を応援するつもりで、給付型奨学金の創設を検討すべきと思うがどうか。
第4に、高齢者対策です。
シルバーパスは、2025年10月1日から、住民税課税は、年間の負担額が12000円に引き下げられました。
荒川区では、都に合わせて10月から70歳以上の全区民が一律1000円で取得できるようにする区独自の補助を始めます。本区としても、もともと無償とされていたものであり、検討すべきと思うがどうか。
2つ目に75歳以上の後期高齢者医療費窓口負担割合2割の方への暫定軽減措置が、今年10月から、一部の人が2割負担となります。物価高騰で実質年金額も下がり、高齢者の生活も更に厳しくなります。区独自の軽減策を実施すべきと思うがどうか。
3つ目に、高齢者が民間賃貸住宅への入居を拒否され、入居困難な問題があります。住まいは人権の立場で、低廉な費用で住まいを提供できる公営住宅を増設すべきではないのか。
4つ目に、特別養護老人ホームの待機者数は、1100人以上です。わが党は、繰り返し、特別養護老人ホームの整備を進めるよう求めてきましたが、入居待機者解消のため特別養護老人ホームを整備すべきと思うがどうか。
5つ目に、2024年度、介護事業所倒産は172社で過去最多で、休廃業・解散も612社と過去最多です。全国の自治体で訪問介護事業所がゼロの自治体が107町村、訪問介護事業所が残り一つの自治体は272市町村です。経営悪化と倒産が相次ぐ危機的状況にあります。前定例会の質疑で、区内介護事業所の倒産や休廃業は把握されていません。
本区は、物価高騰緊急対策費助成を行いましたが、現場では、物価高騰に苦しむ福祉施設に、自治体の制度や支援が追い付いていません。全ての区内介護事業者に物価高騰対策緊急支援金の拡充と実施の延長をすべきではないのか。
第5に、地域交通についてです。
住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けられる、環境づくりを進めていくためにも、移動手段の確保は大変重要であり、支援する仕組みづくりが必要です。
住民の足の確保は、暮らしを守るうえでも重要と言えます。
そこで、
①新小岩地域、特に西新小岩地域は、バス停から距離があり、道路の幅員が狭くて、大型バスを走らせることが困難です。地域乗合バスの検討をしてはどうか。
②休止されているレインボーバスの復活は、地域の悲願であり、事業者に協力要請するとともに、新たな補助事業も検討すべきと思うがどうか。
③公共施設を循環する保健所、ウェルピア、区役所等を検討すべきと思うがどうか。
④区民の移動する権利を保障するために、交通政策課を拡大して、独立した「交通局」を設置し、区が直接交通事業者になって「区民の足」を確保する取り組みを進めていくことを検討すべきと思うがどうか。
次に、災害対策について質問します。
東京でも35℃以上の猛暑日が続き、年間猛暑日は最多記録を更新し、未だ異常な暑さが続く中、深刻な地球温暖化を肌で感じる毎日です。
このまま地球温暖化が進むと、一度台風が発生すると、狂暴な台風に成長すると同時に線状降水帯が発生し、広域で記録的な豪雨をもたらす傾向も増加します。自然災害は避けることは出来ませんが、被害を最小限に抑える防災・減災対策とともに地球温暖化対策を強化することが重要です。
国際的には、気候危機対策に背を向けるトランプ米政権、石炭火力発電を推進する日本政府の姿勢が厳しく問われています。
かつしかゼロエミッションは、30年までにCO2排出を50%削減する目標です。第3次環境基本計画をもっと可視化する必要があります。
たとえば、CO2吸収量を拡大するためには樹木を増やすことが重要です。
①樹木は暑さを緩和し、CO2や大気汚染物質を吸収します。こうした樹木の役割や環境への影響について可視化し、区民と共有することで区民参加の温暖化対策にしていくことが重要と思うがどうか。
②樹木をどれだけ増やすのか、とりわけ公共施設や公園等での本数の計画をもつことが必要だと思うがどうか。
③さらに高木の枝葉が覆う面積割合である樹冠被覆率を高めることは直射日光が当たる道路より路面温度を20度下げると言われ、この樹冠被覆率の目標を持つことが必要だと思うがどうか。
④CO2排出量が多い大型開発は、区内で立石駅周辺、東金町西地区、新小岩駅周辺で進められていますが、これらによるCO2排出量を試算し、それを上回る吸収量のための対策を立てるべきです。
また、奥戸地域では巨大物流センターの建設が進んでいますが、樹木が伐採されました。ここでもCO2排出量の試算、それを上回る吸収量のため対策を立てるべきです。
各地で線状降水帯による内水氾濫の被害が相次いでいます。
ハザードマップなどで事前に避難ルートを確認することを呼びかけることは重要なことです。しかし、線状降水帯は予測が難しく、あっという間に道路にあふれだし川のようになってしまいます。
①大雨警報は、数時間前です。数時間前に垂直避難や縁故避難を促しても、それができないよう配慮者への対応は自助、共助が働かず、公助での対応となると思うが、どのような避難行動となるのか具体的に伺います。
②入口が道路より低い店舗、住宅の場合、浸水すればその後の生活・営業再建に困難が生じます。あるいは地下に電気設備があるマンションも、浸水すれば長期間の停電となり、こちらも生活困難に陥ってしまいます。防水板や防水扉の設置などを促していくことが必要だと思うがどうか。
③排水施設の処理能力があっても、排水溝に落ち葉やゴミなどが詰まっていると十分な排水ができない可能性もあります。排水溝の定期的な清掃や点検を実施すべきと思うがどうか。
災害後の避難所での生活は尊厳ある生活を保障することによって災害関連死を減らすことは可能です。避難所あり方の基準となっているのがスフィア基準です。区は「避難所の環境改善が必要であると認識している」と答弁しているので、その立場で計画を持たなければなりません。
たとえば、避難所・避難生活学会は、災害後48時間以内に、清潔なトイレ、温かい食事ができるキッチン、段ボールベッドのTKB48を推奨しています。
①本区でも今年度、堀切水辺公園に移動できる自己循環型水洗トイレ1基を導入するが、今後の導入計画はどうなっているか。
②避難所における生活であっても人権尊重、プライバシー保護の観点から、世帯ごとのテント、段ボールベッド、パーテーションなどを計画的に確保すべきと思うがどうか。
③第一順位避難所の学校のバリアフリー化を急ぐべきであり、小中学校の改築計画と必要な基金を積立すべきと思うがどうか。
④現在、学校外に2カ所の屋内温水プールを整備するために、今年度から3年間で75億円余の基金取り崩しを計画しているが、そもそもこの基金は、学校の改築や大規模改修に充てるべき基金です。この使い方は学校改築に支障をきたすだけで、計画は中止すべきと思うがどうか。
⑤災害後、長期の停電も予想されます。正確な情報を発信しても受ける側にスマホなどの機器がなければなりません。高齢者や障害者などの要配慮者に、防災ラジオを無償配布してはどうか。
⑥区は、区民に対して日常の備えとして最低3日分の備蓄、できれば1週間分と呼び掛けています。ところが呼びかけている区の備蓄品は1日分です。自助だけでなく、公助の役割を果たすべきです。区としても最低3日分の備蓄,そして区民の3日分の備蓄品を廉価で提供することも検討すべきと思うがどうか。
⑦震災の際に屋内の家具転倒による圧死も多いのが実態です。災害時に火災延焼を防ぐための感震ブレーカーの無償配布に続き、家具転倒防止器具、ガラス飛散防止フィルムの無償配布に踏み出すべきと思うがどうか。
⑧ペットとの同行避難も課題です。東日本大震災では3100頭の犬が犠牲となり、熊本地震でも多数のペットが負傷し放浪状態になりました。能登半島地震では、「ペットがいるから避難所にいけない」と納屋で避難生活をしていた男性が火災により死亡する事件がおきました。過去の悲惨な経験に学び、ペット防災が減災につながることへの意識を高めることが必要です。ペット同行避難を推奨することにより、人も動物も救えることを知らせることが必要と思うが、実際にペットを連れた同行避難の訓練は実施されているか、実施しているとしたらどんな課題があったか。実施できていなければ、今後の計画はあるか伺います。
⑨アレルギーや持病などがある人への配慮から、避難所の選択肢をどう増やしていくも課題と思うがどうか。
次に、巨大開発事業と庁舎問題について質問します。
埼玉大学岩見良太郎名誉教授によれば、介入強化型都市再生によりディベロッパーの利益にはつながっても、国民所得は減少を続け、実質賃金も減り、日本経済が経済成長できない、格差の拡大が広がり続けるという結果になっていると指摘しています。
劇的な矛盾は、不動産価格が急騰、特別区のマンション販売価格が1億円を超し、その原因は、都心を中心にタワーマンションが投機目的で買われ、不動産バブルを作り出しています。
こうしたタワーマンションが再開発により建設するにあたり多額の税金投入が行われています。すなわち、再開発によるタワマンがそのマンション価格を引き上げる要因となり、周辺の地価、賃貸物件の家賃高騰を招き、住み続けられない状態を作り出しています。
こうした状況をどう認識しているのか、答弁を求めます。
千代田区は、マンション高騰の転売の一手として「新築マンションの転売5年間できないようにしてほしい」と不動産業界に要請を行いました。再開発で、巨額の補助金が投入されているわけですから、そういう要請を行うことには、根拠があります。
いま、必要なことは、不動産バブルを作り出しているこうした構造、投機目的による売買の規制を行うことが必要ではないのか。今後、竣工する駅前再開発のタワーマンションに対して、居住目的という条件を明記させる行政指導が必要だと思うがどうか。
加えて、今日的な新たな物価高騰が再開発事業に急ブレーキかけるという状態が生じています。中野サンプラザ周辺の再開発は、野村不動産が断念しました。新宿駅、池袋駅、品川区、北区、船橋駅南口など各地で中断においこまれ、本区でも新小岩駅南口、立石駅南口も足踏み状態になっています。
立石駅北口再開発に、ブレーキがかからないのは、区役所庁舎建設により潤沢な資金供給を保障しているからに他なりません。
再開発事業への補助金の区の負担は、33%から45%であり、都市計画交付金と都区財調で賄われると説明していますが、再開発の竣工時には、一括で支払わなければなりません。
立石駅北口再開発の総工費は、さらに上昇することは間違いありませんが、総事業費について明示していただきたい。答弁を求めます。
今定例会の後、10月末に再開発組合が契約を締結、同時に、保留床取得に係る「協定」も締結されますが、さらに上昇すれば、保留床取得に要する負担と別に200億円超の補助金と公共施設管理者負担金負担が生じることとなります。ほぼ同時期に、東金町1丁目西地区の再開発も竣工時に、同じく100億円超の負担が生じます。
先ほども述べた、区内のその他再開発、新小岩、立石駅南口東地区、西地区の再開発も補助金等はそれぞれ100億円単位の負担が毎年生じることになります。加えて、東新小岩運動場にスタジアム構想が現実にあります。スタジアム建設となると数百億円規模の税金投入が必要になります。
都市計画交付金、都区財調で措置されると言っても、今後、毎年巨額の財政支出を必要とすることになり、財源対策に問題が生じる危険があるのではないか。
区役所庁舎保留床購入で積立金に不足が生じれば、すでに起債を起こすと答弁していますが、そうなれば、他の再開発等で財源が不足する場合、記載とするのか。そうなれば、多額の利払いによる財源不足を生じさせるのではないのか。
また、学校建て替えなど同じく多くの財源を必要とする計画事業が困難となる危険が生じると思うがどうか。
立石駅北口再開発は、現時点で工事契約も区が購入する予定の保留床の「協定」も決定していない、見直し可能な局面にあります。今後、保留床の価格上昇は確実であり、これが新たな財源を必要とする問題をはらみ、保留床価格の向上にとどまる問題ではないのか。
さらに、再開発後も新たな税金投入が必要となります。亀有駅南口では、7階部分は、結局、税金投入によって公共施設とし、今後も続きます。弐番館店舗も空きが多い。金町駅南口ベルトーレ3階も当初計画のない公共施設とせざるを得ませんでした。さらに、金町南口のビナシス2階の双葉会館が撤退しました。再開発後の施設維持にはこういうリスクがあり、これをどう認識し、また、今後の見通しの答弁を求めます。
さる7月22日に立石駅北口再開発の「権利変換計画に異議あり、区民の財産をこれ以上散逸させるな」と5回目の230名以上が原告となり集団住民訴訟が行われ、判決の言い渡しが9月19日となりました。
あと2ケ月余りで、私たちの任期が終了し、区議会議員・区長選挙がたたかわれますが、立石駅北口再開発にかかる区庁舎移転問題も重要な争点であり、強引に進めれば進めるほど区民サービスの低下に直面する危険があります。
改めて、抜本的な見直しを強く求めるものです。
最後に、バルサアカデミー葛飾校の問題についてです。
第1に、事業譲渡の問題です。
区は、当時の副区長を発起人として派遣し「キッズ未来」の立ち上げに関与しており、FCバルセロナも2012年6月20日に「葛飾区が設立した法人であるキッズ未来とともに協働できることを心待ちにしている」と区長に書簡を送るくらい、緊密な関係であったことが明らかになりました。
「キッズ未来」ではなく、区長自身が熱心に誘致しようとしていたわけで、誘致の条件となっていたグラウンドとクラブハウスの継続的な確保のために、夜間照明、トレーラーハウス、人工芝等に総額4億円超の税金投入もしてきたことは、まさに区政の私物化です。
「キッズ未来」は子ども達から集めた月謝を使って毎年高額接待を繰り返し債務超過に陥り、挙句のはてに事業を譲渡しました。この事業譲渡について秋元氏は、「アメージング社」の代表に、グラウンド優先利用を含む協定先が「キッズ未来」から変わらなければ問題ないという小林前副区長の見解をメールで伝え、バルサスクール保護者会代表に対しても小林前副区長と相談を重ね、最終的には事業譲渡が良いという事になったと証言しました。
ところが8月19日の全員協議会では秋元氏は、「相談や助言は受けていない」とこれらの証言を全否定しました。バルサスクール事業の協定先である区に何の相談もしないで事業譲渡したことに対して、「キッズ未来」も区も告発もしない、果たして区は知らなかったと言えるのか。もし知らなかったと言い張るなら、「キッズ未来」が勝手に事業譲渡したことに対し、重大な協定違反として「キッズ未来」を告発すべきと思うがどうか。
第2に、「協定」による優先利用と原則的対応の問題です。
グラウンドの優先利用を許可していた「キッズ未来」と区の協定は、3月末で終了したにもかかわらず、「アメージング社」にグラウンドを貸し続けている。なぜ、協定に明記されている通りに物事を進めるという原則的な立場に立たなかったのか。
地方自治法244条には公共施設の平等利用の原則が定められています。営利企業にグラウンドを優先利用させることは、法律に反します。
わが党は、当初から特定団体への優先利用を認めない立場に立ってきましたが、遅きに失したとはいえ、グラウンドの優先利用は9月末をもって終了することになりました。これを機に、どういう団体が、どういう理由でグラウンドの優先利用をしているのか、精査をする必要があると思うがどうか。
第3に、第3者委員会の調査です。
区議会は、3月27日の決議で真相解明を求めました。今回の第3者委員会の調査結果は、来年3月の報告としていますが、遅すぎるのではありませんか。
6月6日に報告された調査報告書では、政策企画課の当時の関係者、「キッズ未来」の理事長、事業譲渡についての関係者、トレーラーハウスについては監査結果の公表を待って調査となっていますが、3か月たった今、何も報告されていません。すべてが第3者委員会への先送り調査になることは、区議会の決議に背を向けることになると思うがどうか。
調査結果については、今定例会で報告すべきです。 区政に混乱をもたらした責任は区長にあり、その責任を自覚し区長本人の進退を含めた判断を検討すべきではないか、区長の責任ある答弁を求めます。