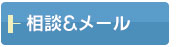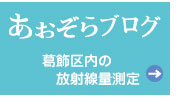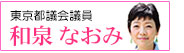学校プール > HOME
- 2022年第二回定例会一般質問 片岡ちとせ
- 2022年第一回定例会代表質問 三小田准一
- 2021年第四回定例会一般質問 中村しんご
- 2021年第三回定例会一般質問 質問者 中村しんご
- 2021年第二回定例会一般質問 質問者 木村ひでこ
- 2021年第一回定例会代表質問 質問者 三小田准一
- 2021年第一回定例会一般質問 質問者 中江秀夫
2022年第二回定例会一般質問 片岡ちとせ
学校プール問題、水泳指導について質問します。
区営・民間温水プールを使う水泳指導が、一部の学校で5月から始まりましたが、問題は山積しています。
第一に、水泳指導の安全性を確保するための定期健康診断についてです。
文部科学省の「水泳指導と安全」のガイドラインでは、学校医による内科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科の各健診の結果を水泳の可・不可の決定をするため、毎学年、6月30日までに健診を終了し、水泳指導を行うよう求めています。
健康管理上注意を必要とする児童・生徒に対し、医師による診断によって水泳が可であることを確かめておかなければならないのは、生命にかかわる問題だからです。
ところが、水泳授業は5月上旬からスタートしたため、この健診が終わらずに水泳指導が行われています。これは児童・生徒の安全管理に重大な影響を及ぼす危険があると思うがどうか。
令和4年度は、四ツ木中学校が最も早く5月6日からスタート、6月30日以前に指導開始をするのが、12校中11校です。
結局、スケジュール先にありきで、水泳指導を行うことは事故にいたる危険をはらむものだと思うがどうか。
第二に、教育委員会のシミュレーションと現場にギャップが生じていることです。
党区議団は、いくつかの学校との面談や温水プールの水泳指導の視察も行いました。ある学校では、1時限からの予定では、バスへの乗車は8時30分ではなく45分から予定し、やってみなければわからないと答えていました。
ある学校では、2~4時限の水泳指導では、給食の時間に間に合わず、遅れて給食を始めることになりました。子どもたちの生活習慣を乱し、関係教職員の負担が出ていると思うがどうか。
また、着衣泳を実施しないという学校もあり、これまでの水泳指導からの後退ではないか。その原因をつくったのは教育委員会の方針ではないかと思うがどうか。
バスの移動では、座席が足りず児童が立ったままという実態がありました。保護者からの問い合わせに区教委は、民間バスの運転手は安全運転だから大丈夫と答えたとのことです。何を根拠に「大丈夫」と言えるのでしょうか。
昨年11月、水戸市内で児童34人が大型観光バスで遠足に向かっていた途中、中央分離帯に衝突し全員がシートベルトをしていたが、2名が軽傷を負う事故がありました。
ある学校では、保育園の近くにバスを停めたために、保育園から「散歩に行きたいが、いつまで停めているのか」と苦情も出ています。
シミュレーション通りにならない現実をどう受け止めているのか、お答えください。
第三に、水泳指導の方針が校舎の建て替えに影響を及ぼしています。
二上小の校舎建て替え基本構想・基本計画が策定されましたが、水泳指導用に大型バス3台を停車させるための、6m×50mの巨大駐車場が図面に示されました。限りある学校の敷地は、教育条件を最大限向上することを前提に計画されなければなりません。しかし、外部の温水プールで水泳指導を行うために、学校のプールは廃止し、駐車場を作る。こうした校舎建設が良いのかと多くの関係者が疑いを抱いています。
子どもたちのための最善の教育環境、長く使う校舎の配置がこれでいいのか、これが今後の学校建て替えのスタンダードになるのか、お答えください。
第四に、コストの問題について伺います。
「今後の水泳指導の実施方法に関する方針」では、児童数の平均値421名として学校外の屋内温水プールを使用した場合、年間507万円でした。
しかし、令和4年度以降の契約では、想定経費のおおむね2倍となり、年間9百万円ほどとなりました。
一方、学校の屋外プールは、80年水道料金も建設費用も上がらない前提のありえない数字ですが、年間770万円です。
議会に対し、事実に反する説明となったことに対して、まずは謝罪すべきと思いますが、どうでしょうか。
また、バス代は一人当たりに換算すると最安624円、最高1319円と2倍以上の開きがあります。施設使用料も区営プールの指定管理者がおしなべて民間プールよりも高くなっています。どうして、このような不合理・不経済なことになるのか、お答えください。
第五に、学校外温水プールを使用しない学校への対策について伺います。
35度超の猛暑日は、8月に集中し、東京の場合、猛暑日は2017年は1日、2018年は5日、2019年、20年、21年はそれぞれゼロでした。さらに、最高気温のピークは、午後3時前後です。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの「学校屋外プールにおける熱中症対策」では、小中学校の熱中症は、プール指導時よりも通常の体育の授業時、中学校では、部活動で発生していることに警鐘を鳴らしています。
暑さ対策のために、学校外温水プール利用に血道をあげることは、はき違いではありませんか。
最も多く熱中症が発生している体育授業時、部活動中の具体策こそが必要だと思うがどうか。
61校は、引き続き、学校プールで水泳指導を行います。その学校の対策がおざなりにされていることも指摘しなければなりません。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの「熱中症対策」では、①プールに日陰、テントや遮光ネット、②扇風機、団扇、③スポーツドリンク、④氷のう、保冷材、⑤サンダル、⑥水面シートなどの実施を奨励しています。
我が区議団はこれまでもたびたび遮光ネットの設置などを提言してきましたが、学校プールを使用する学校で、それぞれの施設がどれだけ熱中症対策を用意をしているのか伺います。
第六に、区民に保障すべき社会教育と学校教育の関係について伺います。
社会教育とは、学校の教育課程として行われる教育活動を除くことが社会教育法で定められています。よって社会教育施設である区営温水プールを学校教育としての水泳指導優先に使うことは誤りだと思うがどうか。
現実に社会教育団体の活動が制限され、犠牲を背負わせています。今後、複数の学校で活用すれば、さらに団体の活用を制限することになります。
社会教育施設で学校の水泳指導はやめるべきと思うがどうか。
金町公園プールを温水プールに改修し、学校の水泳授業以外を一般利用とどうか。することは、二重の誤りです。「基本計画」で温水プールの設置計画を記載しましたが、学校の水泳指導のためではなく、社会教育施設として区民に開放すべきと思うがどうか。
2022年第一回定例会代表質問 三小田准一
学校プールについてお聞きします。
当初予算案には、12校の学校外プール活用のために9千万円が計上されています。しかし、昨年第3回定例会以降、次々に区民から請願が提出され、今定例会にも請願が提出されています。しかも区立温水プールの利用者からだされた請願は、多くの委員からたくさんの意見が出され議会では継続審議になっています。学校外プールの活用に区民合意がないことは明らかです。
わが党は、今月4日に教育長に抗議と是正の申し入れをしましたが、12校の学校外プールの活用計画は、議会軽視も甚だしいと言わなければなりません。教育長の認識を伺います。
学校外プールの活用は、①移動時間がかかり、水泳指導か他の授業に影響を与えるのではないか、②中学校は学校の状況に応じるといいながら、改築懇談会で結論がでていない四つ木中が対象になっているはなぜか、③常盤中はプールの議論がされる前に学校周辺にプールは設置しない趣旨のチラシを配布していることは、学校と住民を無視しているのではないか、④21日の文教委員会の庶務報告について、授業時数が間違っている、中学校についての授業時数について検討していないにも関わらずなぜ学校外プールの活用の対象校になっているのか、⑤学校外プールの活用シミュレーションでは、給食終了後5分後に水泳指導になっているが、子どもに一層の負担を強いるのではないか、⑥来年度12校での学校外プールの活用は、プールがあるのに使わないという無駄使いになるのではないか、⑦西小菅小学校のプールは新しくなるのに、使わないということについて、何のために作ったのか説明を求めます、⑧社会体育施設条例は、「区民の平等な利用」を原則としており、学校優先の利用はできないのではないか、⑨一昨年末、高砂駅南側の民間プールは閉鎖となりました。民間プールが将来にわたって存続の保障がないことを示していますが、そうなった場合、水泳指導を学校教育として保証できなくなるのではないか、以上、教育長の答弁を求めます。
学校外の屋内プールを活用することが、天候に左右されず計画的にでき、インストラクターが教えることで「より良い水泳指導」になるというなら、全校に、ただちに屋根や遮光ネットの設置、指導員の配置、プール管理の業者委託を検討し、学校プールを活用するための予算に転換すべきではありませんか。転換しないとなれば、学校間格差をつくることになるが、格差をつくる目的はなにか、区長の答弁を求めます。
区教委のいう「よりよい水泳指導」は、現在12校しか対象にしていませんので、間違いなく格差が生じます。それでも学校外プール活用に固執するのは、その目的が「より良い水泳指導」ではなく、学校教育にコストをかけたくないという真の狙いがあるのではありませんか。
改めて教育委員会の水泳指導の方針にあるコスト比較を検証してみました。小学校49校で試算されていますが、学校外の民間屋内プールを活用すれば、年間1校当たり507万5千円、学校内の屋外プール活用は、1校当たり770万6千円と、民間プールが270万円安上がりというものです。
学校プールの試算では、80年間で新規建設や大規模改修が盛り込まれていますが、民間プールの試算には、新規建設も大規模改修もせず、利用料金も人件費もバス代も80年間上がらない計算です。現実にはあり得えません。
民間プールは安上がりを強調したいがために、説明のつかない試算をしなければいけなかったのではありませんか。区長の答弁を求めます。
先ほども申し上げた通り、民間プールは将来にわたって存続できる保証はありません。水泳指導を民間に委託し、民間プールの経営が思わしくなければ、立石駅北口地区再開発事業と同様に、莫大な税金投入で救済しなければ、水泳指導を継続することができないではありませんか。
学校における水泳指導というのは、小さいころから水に親しみ、泳ぐ力を身に着け、海や川での水難事故から命を守る教育です。その教育を将来にわたって保障するために学校にはプールが設置されています。学校プールの廃止は、命を守る教育の放棄になるのではありませんか。教育長の答弁を求めます。
東京消防庁は、学校プールは消防水利にとって重要だという認識を示しています。防災に強い地域を作っていくためにも学校プールは必要と思いますが、区長の答弁を求めます。
2021年第四回定例会一般質問 中村しんご
学校プール問題について質問します。
まず、学校プール廃止のデメリットがいよいよ広がっているのに、矛盾が広がり続けています。
先の定例会でも、移動時間と安全が保てない、区営であれ民間であれ温水プールを利用する一般利用者への使用制限、災害時に活用できないなどです。
こうした矛盾は、新たに温水プールを設置しても、解決できません。
先の定例会では水元小プールの請願は議会の意思として継続となりましたがどう受け止めているのか、答弁を求めます。
水元小プールの存続を求める団体は、区営水元温水プールを管理する指定管理者のインストラクターは募集には、「普通に泳げる程度で問題ない」と指摘しています。しかも現場の教師が水泳インストラクターに「業務上の指示や命令はできません」これを無視すると「偽装請負」となる認識はありますか。教育長をはじめ、インストラクターによりよい水泳指導ができると強調してきたことは不適切です。いま、必要なのは、こうした説明のつかない答弁をくりかえしてきたことを「反省する」ことなのではありませんか。
過日、二上小問題住民の意思を無視した基本構想・基本計画が11月17日付で届きました。10月5日の住民説明会では、プールをなくすことに全員が反対していました。D案というのはマンションの真横になり、その住民が反対を表明しているのにお構いなしでの決定です。住民の意見に耳を傾ける姿勢が問われています。この基本構想・基本計画は撤回すべきです。
四つ木中・小学校の建替え懇談会は、やはり、プールの設置について問題となり、これまで10回の懇談会が行われました。そしてたどり着いたのは、プールの設置については棚上げにしたまま、基本構想・基本計画をつくろうとしています。こんな支離滅裂なことはやめ、プールをつくる計画として明記すべきです、答弁を求めます。
地域の郷土史のパンフレットに木根川小初代プールは、昭和31年に区内小中学校では、11番目に開設され、当時の新聞記事も紹介されています。工事費は、270万円、内訳は、区が90万円、PTAと地元町会有志が一体になって作った建設協賛会が180万円を集めて建設したものでした。まず、こうして、地元との協力で設置されたプールがどれだけあるのか伺います。こうした歴史をどうとらえるのか、答弁いただきたいと思います。
これは、区長・区議選の最中にある小学校の近隣にまかれたチラシです。
10月31日から11月6日までの7日間が、区長・区議選が行われていました。梅田区長候補もわが党の候補者も他の候補者も「学校プールを守れ」と訴えていました。
ところがプールをなくす宣伝物が白昼堂々と中立・公正であるべき公務員によって配付されたことは、選挙妨害以外の何物でもありません。
まず、この配布に要した税金はいくら投入されたのか。区長の意思で配布させたのか。 そうでなければ、地方公務員違反の越権行為を行った職員を処分すべきではないか。それぞれ答弁を求めます。
2021年第三回定例会一般質問 質問者 中村しんご
「今後の水泳指導の実施方法に関する方針」についてです。
まず、8月27日の教育委員会第9回臨時会で議論された「今後の水泳指導の実施方法に関する方針の実施計画(案)について」です。
区教委は、これまで改築校について学校外プールを活用するとし、「当面の間は区内にある既存の施設で十分受入れが可能だ」、そして「当面の間」について、「長いスパン」と答弁していました。
ところが、この「実施計画案」では、金町公園プールを令和7年度から、もう一か所を令和9年度から利用できるように屋内温水プールとして整備するとしています。これは、あまりにも唐突で、議会答弁との整合性もありません。
なぜ、「実施計画案」なのか。本来ならたたき台や素案があり、教育委員会での議論、小中学校校長会の意見聴取、文教委員会での議論がなされて「案」がでてくるのが当然です。
区長は、先ほどの所信では一言も触れていませんが、どういう経緯で突然実施計画案になったのか、時系列で答弁を求めるものです。
2か所の温水プールの整備は、今定例会に提出されている前期実施計画案の「区民のスポーツ活動の促進につなげていくため、適切な施設整備を推進」する項目に盛り込まれています。そうであれば歓迎されるものです。
しかし、区教委の「実施計画案」では、新たな温水プールは、1か所で10校程度の学校における水泳指導のためで、一般区民は、空いているごくわずかな時間しか利用できません。前期実施計画案との齟齬があると思いますが、答弁を求めます。
改築校以外の移行は31校です。移行するまでの間、屋根も付けず、遮光ネットも張らなければ、天候不順によって計画的な水泳指導はできません。また学校外のプールを活用すれば、インストラクターが配置される、プール管理も不要だといいますが、移行までの間、水泳指導の格差を放置するつもりですか。
屋根や遮光ネットは暑さ対策とともに、外部からの視線の遮断にもなります。積極的にとりくむべきです。学校内でもインストラクターの活用やプール管理のための人員配置をすべきです。答弁を求めます。
新たに整備する2か所の室内温水プールは、あくまでも区民のスポーツ活動を促進するためのものにしなければなりません。
金町公園プールを室内温水プールに改修する3年ほどの間は利用できなくなります。鎌倉公園プールを廃止し、今度は、金町公園プールも利用させない、2重の誤りです。
誤りを繰り返さないためにも、わが党が要求してきた、鎌倉公園プールの跡地に室内温水プールを整備すれば、金町公園プールも継続して利用できます。しかも鎌倉公園プールは、すでに解体され、更地になっていますので、整備する期間も短縮できますが、いかがですか。
区教委の「計画案」は、明らかにつじつま合わせであり、現実性がありません。撤回すべきです。教育長の答弁を求めます。
次に、学校プール廃止による弊害についてです。
一つは、移動時間の問題と安全確保です。
区教委は、水元小の場合、往復30分程度かかると言いますが、指導要領が示す水泳指導の時間を確保できるのでしょうか。各学校の「運用で」というのですが、それは他の授業や学校生活にしわ寄せがいくということにほかなりません。「方針」を出しておいて「運用で」というのは、あまりにも無責任だと思うがどうか。
二つ目は、一般利用者の排除につながるということです。
水元小が水元体育館を使う際、休館日は月に1日だけです。区の説明では、二コマずつ一日3学年分、10週間で全学年が10時間できると言います。その分、一般利用者は使えません。2校受け入れるとなれば、さらに一般利用が減ります。
もともと、水元スポーツセンターの温水プールは、清掃工場の地域への還元施設として生まれたもので、その地域の一般利用を排除することは、到底理解を得られません。
水元小、道上小の建替え時に学校内に室内温水プールを設置すれば移動時間も含めて解消できるではありませんか。
三つ目に、災害時の活用ができないことです。
東京消防庁は、「震災時には常時貯水された水利が必要」として現在の250トンの学校プールをあげていますが、区は、どう認識しているか、答弁を求めます。
この間、中学校長の間では、「プールを学校内につくるべき」との意向と聞いています。この点から言っても。水泳指導の実施方針は撤回すべきだと思うがどうか。
2021年第二回定例会一般質問 質問者 木村ひでこ
次に、学校プールについて伺います。
先の第一回定例会では区教委の「今後の水泳指導の実施方法に関する方針」に対し、代表質問・一般質問、文教委員会などで様々な意見が出され、予算審査特別委員会では各会派の意見で、「再考を強く求める」「十分な議論を」「白紙撤回すべき」など議論し直す必要があるとし、「賛成する」と示したのは少数派でした。まさに、議会での審議をまともに行わず、区教委が一方的に方針決定をしたことに他ならず、議会軽視です。
この現状について、区長および、教育長はどのように受け止めているのでしょうか、それぞれ答弁を求めます。
現在策定中の区基本計画素案のパブリックコメントでも、学校プール廃止反対が多数ありました。ある弁護士は、水元小、道上小の問題では「説明・協議なしで進められている点に、手続き的瑕疵がある」と指摘しています。
水元小学校の基本設計案が4月23日に説明会が開催されました。しかし、プール設置案を住民に示した後、プールなしの基本設計をつくることに道理はありません。しかも「まん延防止重点措置」中で、事前に市民団体から説明会開催延期の要望が出されたのに、これを無視して開催しました。
当日は「なぜ、道上小学校や二上小学校では説明会を延期しているのに、水元小だけ強行なのか」など意見が続出しましたが、まともに答えず、説明を始めました。結果、質疑時間は30分ほどで、はじめから、住民の意見を開く姿勢が見られませんでした。
いまの設計は直ちに保留にし、現在も緊急事態宣言下にありますが、落ち着いた時点で、あらためて、きちんと広い会場を確保し、時間をかけて住民説明会を行うべきだと思うがどうか。
こうした不満の声が上がっているのは、水元小だけではありません。
道上小では「プールをつくらないことをはじめて聞いた」など、多くの保護者が困惑しています。道上小の2年生の児童が「去年はコロナでプールに入れなかったけど、プールがなくなっちゃうんですか」と悲しんでいました。
次に、この間の議会でのやり取りでは「今後検討してまいります」との答弁ばかりが目につきます。そこで、以下、伺います。
第一に、将来にわたってすべての小学校が改築した際には、小学校内にプールがなくなります。どうやって2つの区立総合体育館と民間の温水プールを使って水泳指導を行うのか。
第二に、「方針」では、「水泳指導を学校外で実施していく意向のある学校については、学校外プールの活用へと移行していく」とあるが、具体的に学校外プール活用の意向のある学校はあるのか。区教委として、積極的にすすめているのか。
第三に、夏休みの間の学校での子どもたちの水泳指導をどのように実施するのか。
第四に、一般利用者とのすみわけをどのように考えているのか。
第五に、第一回定例会一般質問での学校プールへの屋根や遮光ネットの設置について、「必要であればネットを張るということも考えられる」と答弁しました。具体的な設置計画を示してください。そもそもどこの学校でも必要と思うが、答弁を求めます。
次に、3月16日の文教委員会で教育長が、「子どもの権利条約12条にあるのは、意見表明権を保障するということで、そのことをもって、子どもの意見を聞かなければならないという解釈はできない」と、答弁したことについてです。
子どもの意見表明権を研究している佛教大学永瀬正子准教授は、コロナ禍で全国一律休校という措置が取られたことについて、「子どもに説明なく、意見を聞かないまま決定がなされた。その説明をすべて親が負担しないといけない事態に怒りがあった。」と振り返ります。国連子どもの権利委員会の昨年4月8日の声明には、どんな時も子どもの「声」を聴くことの重要性を強調しています。
教育長は、今回の発言について真摯に反省し、誤りを認めるべきです。区長自身、この教育長の発言をどのように受け止めているのか、それぞれの態度表明をお聞かせください。
2021年第一回定例会代表質問 質問者 三小田准一
次に、学校プールの廃止方針について伺います。
教育委員会は、昨年10月13日「今後の水泳指導の実施方向について」を議論し、12月25日に決定しました。
その内容は、今後の水泳指導は区立の温水プールや民間プールを活用し、小学校にプールは設置しない、中学校は学校の状況による、大規模改修は実施しないというもので、学校プールを廃止する方針です。
50年以上にわたって続いてきた学校プールを活用しての水泳指導を、たった1回の議論で変えるのは極めて乱暴であり、学校プール廃止を打ち出したのは23区で葛飾区だけです。
まず、区長にお聞きします。
「学校改築の基本的な考え方」では、「学校施設は、子ども達の学習・生活の場という基本的な教育条件の一つ」と同時に、「生涯学習、文化、スポーツなどの活動の場として利用される最も身近な地域コミュニティーの拠点」「災害時には、地域の避難所として利用される重要な役割を担う、地域の核となる重要な公共施設」としています。
要するに、学校プールも含めた学校施設は、教育と地域からの視点が重要だということです。したがって改築にあたっては、児童・生徒、教職員、地域住民の幅広い意見を聞き、合意に基づいてすすめることが必要ですが、そのプロセスが一切ありません。
教職員については、説明も意見聴取もされておりません。当事者である児童・生徒についてもいっさい意見を聞いていません。
どういう学校をつくるかの基本構想・基本計画の検討は、そもそも懇談会形式で区教委、学校関係者、設計関係者と町会長など15人前後で進められます。
「案」が策定されてからの説明会は、保護者と学校から30m以内と限定され、極めて閉鎖的です。
子ども、教職員そして学区域まで広げて地域住民から意見を聞くべきではありませんか。区長の答弁を求めます。
教育委員会は、民間プールを活用するメリット、デメリットをあげています。メリットについてお聞きします。
複数の専門のインストラクターがつき、プール管理も不要で、学校の負担が軽減できるとしています。
しかし、これは議論のすり替えです。学校現場からは、長年、人の配置が要求されてきました。それを拒んできたのは区教委ではありませんか。
教員の負担軽減が必要と判断するならば、専門の指導員やプール管理の人員を学校に配置すべきです。
民間プール活用は経費削減になるとしています。
民間プールの活用は年間500万円、学校プールは年間770万円と試算し、民間プールが安上がりと強調しています。
学校改築には、都の財調算定があり財源が措置されています。その中にはプールの改築費用も含まれており、1校当たり小学校は1億1600万円、中学校は6600万円です。プールを改築してもしなくても措置されますので、改築しないのは、税金の使い方の主旨に反するのではありませんか。
天候に左右されない計画的な水泳指導ができるとしています。
教育的見地から屋内温水プールが水泳指導に適しているというなら、今後の改築校は屋内温水プールを検討し、改築の際の財調算定を温水プールにするよう都に求めるべきです。当面の対応として学校プールに屋根を設置すべきです。それぞれ教育長の答弁を求めます。
次に、デメリットについてです。
移動時間、移動時の安全確保をあげています。
移動時間がかかれば、結果として、他の学習時間に影響を及ぼします。実際、改築中の中学校では、学校外の体育館を活用して体育の授業をしましたが、移動時間がかかり、授業時間を短縮しました。
移動はバスも検討しているようですが、改築中の小学校では、学校外プールへバスでの移動でしたが、予算がとれず、15分間徒歩での移動を強いられました。
子どもの中には通常と異なることに緊張や興奮など、様々な反応を示す子もいます。移動といっても物ではありません。特別支援学級の介助員は移動に付き添うことはできません。
区教委の「考えながら運用ができる」という姿勢は、子ども達を犠牲にし、事故につながることになりませんか。
夏季休業中の水泳指導は「難しくなる」としています。
夏季休業中は、任意の参加ですが、授業を補い泳力の到達を引き上げるためです。9月の水泳記録会は、水泳指導の集大成となります。学校ごとに民間プールでばらばらの水泳指導になれば、この記録会はできません。
ある小学校教諭は「自校で指導できなければ岩井臨海学校には連れて行けない」と語っています。
夏季休業中の水泳指導や水泳記録会ができなくなるのは、水に親しみ、泳力を身に着け、海や川での事故から子どもの命を守るという教育を否定することになりませんか。
災害時の対応があげられています。
13日に発生した福島県沖地震では、火災と断水の被害も出ました。学校プールは、災害時の貴重な消防水利となっていますが、消防署との協議はどうなっていますか。学校プールは、水害時に活用するゴムボートの訓練の場ですが、区教委は、「川で対応できる」と強弁しています。川での訓練は、かえって危険であり、災害時の公助を投げ捨てることになりませんか。ここには自助、共助を強調し、自己責任を押し付ける姿勢が伺えます。
施設開放が「難しい」としています。
これほど区民を侮辱するものはありません。
鎌倉公園プールの廃止を強行し、その代替として東柴又小学校プールを開放しましたが、そのプールを廃止する方針は、区民をあざむくことになりませんか。
今後、子ども達や地域住民が泳ぎたい時には、民間プールで高い料金を払っての利用となり、プールで泳げるかどうかは自己責任、区がスポーツ格差をつくることになりませんか。
区立の温水プールにしても民間プールにしても一般の利用者がいます。学校が利用する時は、当然利用できません。区民の生涯スポーツを否定することになりませんか。それぞれ教育長の答弁を求めます。
今年竣工する本田中と小松中は、民間プールの活用について、移動時間の問題や民間プールは恒久的ではないとの検討からプールを設置しました。であるならば小学校も同様ではありませんか。学校プールを設置しないという方針には道理がなく撤回すべきです。
昨年3月、文科省は、学校施設の老朽化対策として、学校施設と他の公共施設の集約化、近隣学校の共同利用、民間施設の利用の重点化が進んでいないとし、学校プール廃止の事例をあげました。
この国の動きが、青木区政の公共施設のリストラ計画に拍車をかけ、現在策定中の基本計画素案に学校プール廃止方針を盛り込もうとしていますが、到底認められません。削除すべきです。
学校プールの廃止は、コロナ禍のもとでストレスを抱える子ども達に最悪のメッセージです。改めて撤回を求めます。区長の答弁を求めます。
2021年第一回定例会一般質問 質問者 中江秀夫
次に、学校プールについて伺います。
昨日のわが党代表質問でも、問いました。
「今後の水泳指導の実施方法に関する方針」について撤回することを改めて求めるものです。
その上で、第一に、水元小学校における設計変更を白紙に戻すべきです。
この件について知らされているのは「改築設計懇談会」の出席者だけです。メンバーは校長、副校長を含め14人だけ、少なくとも1月14日までは学校の教職員にすら何も伝わっていません。直接かかわる学校関係者の意見も聞かず、決めてしまうという態度です。
水元小学校の改築にあたって2019年10月に住民説明会を開催しました。その際示された「基本構想・基本計画」には4階屋上にプールが描かれていました。ところが、「改築設計懇談会」にしめした資料にはプールがなくなっているのです。その上、すでに基本設計の策定作業をすすめ、出来上がってから住民説明会をすると言います。とんでもありません。一度説明をした内容と異なる事をすすめようとしているのですから、まずはそのことを伝え、意見を聞くべきです。特に、今度の区の提案は、学校の水泳指導を行う際に、水元総合スポーツセンターの温水プールを使うとしています。そうなれば、多かれ少なかれ、現在スポーツセンターの温水プールを利用している地域の方々にも影響することになります。二重の意味で、無責任です。住民説明会を開かず、かってに方針を決め、基本設計までつくろうとしているのは言語道断です。
水元小学校改築にあたり、関係者の合意の無いまま、学校内にプールをつくらないことについて白紙にすべきです。見解を伺います。
第二に、改築の際には、きちんとプールを設置することです。児童・保護者からは、「水泳授業は命を守るための教育です。時間削減などがないように、学校内の施設で行うのが当たり前だと思います」など、プール設置が当然とする意見が多数寄せられています。この子どもを預ける保護者の声にこたえ、学校にプールを設置することを明言してください。
第三に、熱中症対策として屋根の設置などを求めます。
現在改築計画をすすめている学校も含め、今年の夏の水泳指導に当たって、最大限の熱中症対策などを講じるべきです。そもそも、今回の区が打ち出した方針は、「子どものことを考えて」と盛んに強調しますが、そうであるならば、当然です。
現在、東金町小学校の改築工事が行われていますが、竣工は今年8月です。9月の水泳指導に間に合うように、屋根の設置を追加で行うべきです。沖縄県糸満市の兼城(かねぐすく)小学校は2018年4月に改築され、屋上4階に遮光ネットが張られたプールが設置されました。佐賀県鳥栖市の基里(きざと)小学校が一昨年夏から取り組んでいる“遮光ネットプール”が学校関係者から注目されていて、水温やプールサイドの温度を下げるなどさまざまなメリットが見つかったと報じられており、費用も13万円余だったとのことです。この鳥栖市では、市内学校に遮光ネットを設置しています。【パネル表示】写真は、鳥栖市麓(ふもと)小学校のプールの様子です。本区でも、区内全ての小中学校に遮光ネットを設置すべきと思いますが、いかがですか。
【パネル表示】独立行政法人日本スポーツ振興センターの「学校屋外プールにおける熱中症対策」では、体を冷やすための氷や冷却用タオル、団扇(うちわ)、スポーツドリンク、児童生徒などの足を守るためのサンダルなどの用意、高温多湿となる更衣室へのエアコン設置などが示されていますが、こうしたとりくみもおこなうべきです。答弁を求めます。
第四に、天候不順対策として、加温式プールの設置も計画的にすすめてはどうでしょうか。
都立水元小合学園では、温水プールではありませんが、水泳部もあり、5月~11月にプーリ利用をしています。水温が低い時には加温式になっていて、通常に比べ4~5度程度水温が上げられるといいます。一気に全校に設置するのは難しいかもしれませんが、計画的に設置すべきです。答弁を求めます。